ゲームボーイとゲームボーイカラー専用ソフトの国内売上ランキングトップ10がわかります。
みなさんこんにちは、syuyaです。
みなさんは、任天堂より発売されていたレトロ携帯ゲーム『ゲームボーイ』と『ゲームボーイカラー』をご存じですか?
ゲームボーイは、1989年4月21日に任天堂から発売された携帯型ゲーム機で、乾電池で動作しながらも本格的なゲーム体験を提供するというコンセプトのもと登場しました。
白黒のドットマトリクス液晶を採用し、当時としては画期的な長時間駆動と頑丈な設計で人気を博し、『テトリス』『ポケットモンスター』などの大ヒット作を通じて、子どもから大人まで幅広い層に浸透しました。
また、その後継機であるゲームボーイカラーは1998年10月21日に発売され、従来のソフト資産を活かしつつカラー表示と処理能力の強化を実現。
ゲームボーイと共に、90年代を代表する携帯ゲーム文化を築き上げ、全世界で1億1千万台以上を売り上げる伝説的シリーズとなりました。
携帯性とソフトの豊富さ、そして丈夫さが組み合わさったこのシリーズは、”持ち運べる任天堂”の象徴として、長く愛され続けたのです。
この記事では、そんなゲームボーイとゲームボーイカラー専用ソフトの国内売上販売数トップ10をご紹介します。
*販売数は概算であり、集計方法などにより数値が異なる事があることを、ご了承ください。
1位:ポケットモンスター 赤・緑・青・・・822万本
| タイトル | ポケットモンスター 赤・緑・青 |
| 発売日 | 1996年2月27日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 822万本 |
日本国内で最も売れたゲームボーイ専用ソフトは『ポケットモンスター赤・緑・青』です。
売上げ販売数は822万本となっています。
『ポケットモンスター 赤・緑』は1996年2月27日、ゲームフリークが開発し、任天堂からゲームボーイ向けに発売されたロールプレイングゲームで、日本における“ポケモンブーム”の原点となった作品です。
プレイヤーは、カントー地方を舞台にポケモントレーナーとして旅に出て、151種類のポケモンを集めながら、ジムリーダーとのバトルやライバルとの対決を通してポケモンリーグの制覇を目指します。
最大の特徴は、ゲームボーイ同士を”通信ケーブル”で接続し、他プレイヤーとポケモンの交換や対戦ができる点で、赤と緑では出現するポケモンが一部異なる仕様になっており、全てのポケモンを集めるには他人との協力が必須という設計が、当時の子どもたちの間で大きな話題を呼びました。
その後、グラフィックやテキストの修正、ポケモンの出現バランスの調整などを施したバージョン『ポケットモンスター 青』が、1996年10月15日に『コロコロコミック』誌上の限定販売として登場し、1999年には一般販売も開始されました。
赤・緑・青は、ゲームボーイのハード性能を最大限に活かしつつ、単なる育成や収集ではなく“対戦”と“交流”の面白さをゲームシステムに組み込んだ先駆的な作品であり、発売当初はじわじわと口コミで人気が広がっていき、やがて爆発的ヒットとなります。
累計販売本数は国内だけで800万本以上、全世界では2900万本以上を記録し、その後のアニメ化や映画化、カードゲーム展開など、ポケモンという世界的IPの出発点となりました。
バージョンアップ版である『ピカチュウバージョン』も含めた世界累計売上は4601万本に達し、これは2024年時点においても歴代ゲームソフト売上ランキングでトップ10に入る売上げを記録しています。
シンプルなグラフィックの中に奥深い戦略性を秘め、今なおシリーズ作品に受け継がれている基本的なゲーム構造――タイプ相性、進化、技の選択、バトルの駆け引きなど――を初めて形にした『赤・緑・青』は、まさに「子どもの日常を変えたゲーム」として、ゲーム史に不朽の名を残しています。
2位:ポケットモンスター金・銀・・・608万本
| タイトル | ポケットモンスター金・銀 |
| 発売日 | 1999年11月21日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 608万本 |
日本国内で2番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『ポケットモンスター金・銀』です。
売上げ販売数は608万本となっています。
『ポケットモンスター 金・銀』は、1999年11月21日にゲームボーイカラー対応ソフトとして発売された、ポケモンシリーズ本編の第2世代作品です。
前作『赤・緑・青』の爆発的ヒットを受けて開発された本作は、舞台をカントー地方から離れた新地域ジョウト地方へと移し、新たに100種類のポケモンが追加され、総勢251匹のポケモンが登場する大ボリュームの内容となりました。
ゲームボーイカラーに対応しているものの、ゲームボーイ互換機でも遊べる設計となっており、旧来のユーザーも取り込みながら、新ハードの色彩表現や処理能力を活かした演出が加えられています。
本作では、”オス・メスの性別””時間帯(朝・昼・夜)””ポケモンの持ち物””なつき度”などの新要素が多数導入され、育成や進化の幅が格段に広がりました。
また、”ふしぎなタマゴ”からポケモンを孵すシステムや、曜日ごとに発生するイベントなど、世界が生きているかのようなリアリティを持たせた設計も革新的でした。
さらに、ゲームを進めると前作『赤・緑』の舞台であるカントー地方にも渡航できるという構成は、多くのプレイヤーに衝撃を与え、”続編でありながら前作の完全版でもある”という贅沢な作りで長く語り継がれています。
対戦面でも、新たな「はがね」「あく」タイプの登場や、能力の個体差(個体値や努力値)といった裏の育成要素が少しずつ意識され始め、のちの対戦文化の土台となる戦略性が強化されました。
また、ラジオや携帯電話(ポケギア)といった現代的な要素も導入され、冒険の自由度と生活感がよりリアルに演出されています。
『金・銀』は発売当時から非常に高い期待を集め、発売初週だけで約140万本を売り上げ、最終的には日本国内で600万本以上、全世界で2300万本を超える大ヒットとなりました。
初代の魅力を丁寧に引き継ぎながらも、次なる世代への橋渡しとして新しい仕組みを数多く取り入れた『金・銀』は、”ただの続編”ではなく、ポケモンというシリーズの進化を決定づけた重要作として、今もなお根強い人気を誇っています。
シリーズ全体においても屈指の完成度と評価される、まさに第2世代の金字塔的作品です。
3位:テトリス・・・423万本
| タイトル | テトリス |
| 発売日 | 1989年6月14日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 423万本 |
日本国内で3番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『テトリス』です。
売上げ販売数は423万本となっています。
ゲームボーイ版『テトリス』は、1989年6月14日に任天堂から発売されたパズルゲームで、同年に登場した携帯型ゲーム機・ゲームボーイ本体と同時に発売されたソフトのひとつです。
もともとは1984年にソ連で開発された作品ですが、任天堂がその版権を獲得し、家庭用・携帯用に最適化されたことで世界的なブームの引き金となりました。
中でもこのゲームボーイ版は、当時の携帯機としては異例の“対戦機能”を持っており、専用の通信ケーブルを使うことで、2台のゲームボーイでリアルタイム対戦が可能となっていた点が画期的でした。
プレイヤーは、様々な形をしたブロック(テトリミノ)を落下させ、横一列に並べて消していくというシンプルなルールながら、次第にスピードが上がり、瞬時の判断力と空間認識力が問われる奥深いゲーム性により、子どもから大人まで幅広い層に受け入れられました。
なかでも、ラインを4つ同時に消す「テトリス」が決まったときの快感は、多くのプレイヤーを夢中にさせ、中毒性の高さでも知られています。
このゲームボーイ版『テトリス』は、ハードの普及に決定的な貢献を果たしたソフトでもあり、”テトリスがあったからゲームボーイが売れた”とも言われるほど。
実際に、ゲームボーイ本体に同梱されていた国も多く、全世界で3500万本以上を売り上げ、携帯ゲーム市場における“キラータイトル”の先駆けとなりました。
電子音楽と単色ドットの組み合わせながらも没入感のある体験は、今日に至るまで“シンプル・イズ・ベスト”の象徴として語り継がれており、ゲームボーイ版『テトリス』はゲーム史における金字塔のひとつとして、今なお語り継がれる存在です。
4位:スーパーマリオランド・・・415万本
| タイトル | スーパーマリオランド |
| 発売日 | 1989年4月21日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 415万本 |
日本国内で4番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『スーパーマリオランド』です。
売上げ販売数は415万本となっています。
『スーパーマリオランド』は、1989年4月21日にゲームボーイ本体と同時に任天堂から発売された、マリオシリーズ初の携帯型作品であり、ゲームボーイのローンチタイトルのひとつでもあります。
開発は、宮本茂氏ではなく、任天堂の横井軍平氏が率いた開発チーム”R&D1”によって行われたことでも知られており、そのためか、ファミコン版『スーパーマリオブラザーズ』とは一線を画す独自の世界観と演出が特徴です。
物語の舞台はサラサ・ランドと呼ばれる異国風の世界で、マリオはピーチ姫ではなくデイジー姫を救うために冒険します。
全4ワールド・全12ステージという比較的コンパクトな構成ながら、ピラミッドや海底遺跡など多彩なステージが用意されており、当時としては斬新だった横スクロールシューティングのような自動スクロール面(潜水艦や飛行機に乗って戦うステージ)も存在します。
また、BGMも高い評価を受けており、ゲームボーイの音源を活かした軽快で独特な旋律は、今でもファンの間で根強い人気があります。
操作性は『スーパーマリオブラザーズ』に準拠しており、ジャンプやファイアボールなど基本アクションは踏襲されつつも、ファイアボールがバウンドするなど、細かな違いもあります。
また、敵キャラクターも亀ではなく「スフィンクス」や「ロボット」など、エジプトや中国を思わせるような異国情緒のあるデザインが多く、独自色の強い作品となっています。
『スーパーマリオランド』は、ゲームボーイ初期のキラータイトルとして、ゲームボーイの普及に大きく貢献し、世界累計で約1800万本以上を売り上げました。
これは、ゲームボーイ用ソフトの中でも『テトリス』に次ぐ販売本数であり、携帯型マリオゲームの可能性を切り開いた記念碑的なタイトルです。
小さな画面とモノクロ表示という制約の中で、いかにマリオらしいアクションと冒険感を表現するかに挑戦した意欲作であり、シリーズの中でも異色ながら、今なお高く評価されている一本です。
5位:スーパーマリオランド2 6つの金貨・・・263万本
| タイトル | スーパーマリオランド2 6つの金貨 |
| 発売日 | 1992年10月21日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 263万本 |
日本国内で5番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『スーパーマリオランド2 6つの金貨』です。
売上げ販売数は263万本となっています。
『スーパーマリオランド2 6つの金貨』は、1992年10月21日にゲームボーイ用ソフトとして任天堂から発売された、マリオシリーズの携帯機向け第2作です。
前作『スーパーマリオランド』から3年半の歳月を経て登場した本作は、グラフィック、アクション、演出すべての面で大幅に進化しており、ゲームボーイ用アクションゲームの中でも特に高い完成度を誇る一本として知られています。
物語は、マリオが冒険から帰還したところ、自身の住む”マリオ城”が謎の敵ワリオに乗っ取られていた、という衝撃的な導入から始まります。
プレイヤーは、ワリオが施した封印を解くために、”6つのゾーン(ステージ群)”を巡り、それぞれのボスから“金貨”を取り戻していくという構成になっており、ステージを自由な順番で攻略できるという、非線形型のゲームデザインが採用されています。
この“6つの金貨”という収集要素と探索の自由さが、より冒険的なプレイ感をもたらしており、従来のマリオシリーズに新たな風を吹き込んでいます。
グラフィックはゲームボーイとは思えないほど精細で、マリオのアニメーションもなめらかになり、背景や敵キャラにも細かな描き込みが見られます。
また、新たに導入された”バニーマリオ(にんじんアイテムで変身)”では、空中でふわりと滞空するアクションが可能になり、より立体的なステージ攻略が求められるようになっています。
サウンド面でも、軽快で親しみやすいメロディが多く、プレイヤーの記憶に残る楽曲が揃っています。
そして本作で初登場したワリオは、以後任天堂の看板キャラクターとして独立し、『ワリオランド』シリーズへと派生していくことになります。
その意味でも、『スーパーマリオランド2』は単なる続編ではなく、任天堂キャラクター史における分岐点でもありました。
販売面では、日本国内で約260万本、世界累計では約1100万本以上を売り上げ、ゲームボーイ用ソフトの中でも屈指のヒット作となりました。
前作と比べてスケール、密度、自由度、表現力のすべてが格段に向上しており、ゲームボーイという制約の中で、マリオ本編に匹敵するゲーム体験を作り上げた、隠れた名作として高く評価されています。
6位:ポケットモンスター ピカチュウ・・・229万本
| タイトル | ポケットモンスター ピカチュウ |
| 発売日 | 1998年9月12日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 229万本 |
日本国内で6番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『ポケットモンスター ピカチュウ』です。
売上げ販売数は229万本となっています。
『ポケットモンスター ピカチュウ』は、1998年9月12日にゲームボーイ用ソフトとして任天堂から発売された、いわゆる『赤・緑・青』に続く初代ポケモンのマイナーチェンジ版にあたる作品です。
正式名称は『ポケットモンスター ピカチュウバージョン』であり、人気アニメ『ポケットモンスター』のテレビシリーズが社会現象的なブームを巻き起こしていた中で、その内容をゲームに落とし込むことを意識して制作されたタイトルでもあります。
最大の特徴は、ゲーム開始時のパートナーがピカチュウで固定されており、しかもそのピカチュウが主人公の後ろをついて歩くという点です。
これはアニメでの主人公サトシとピカチュウの関係性を再現したもので、プレイヤーはピカチュウの感情表現(振り向いたり怒ったり喜んだり)を見ることができ、当時の子供たちに強い愛着を与えました。
さらに、このピカチュウは進化(ライチュウへの進化)を拒否する仕様となっており、まさにアニメ版のピカチュウをそのまま再現した存在になっています。
ゲーム内容としては基本的に『赤・緑』と同様ですが、一部のジムリーダーの手持ちや登場ポケモン、マップ上の配置などに変更が加えられ、アニメに登場したキャラクター”ロケット団のムサシとコジロウ”も登場するなど、細かな演出でアニメファンを取り込む工夫がなされていました。
また、序盤で3匹の御三家(フシギダネ、ヒトカゲ、ゼニガメ)をすべて入手できるようになっており、これもアニメでサトシが3匹を仲間にしていた展開を踏まえた演出といえます。
『ピカチュウバージョン』は、アニメとゲームが双方向に影響を与え始めた最初の試みであり、以後の「ポケモン=ピカチュウ」というブランドイメージの定着に大きな影響を与えたタイトルでもあります。
国内では約229万本、全世界では1400万本以上を売り上げ、初代ポケモン人気をさらに強固なものとしました。
ピカチュウというキャラクターの国民的な定着、そしてゲームとアニメの橋渡しを果たしたという点においても、本作はポケモンというメディアミックス展開の中で、極めて象徴的な位置を占める作品となっています。
7位:遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記・・・221万本
| タイトル | 遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記 |
| 発売日 | 2000年12月7日 |
| メーカー | コナミ |
| 国内販売数 | 221万本 |
日本国内で7番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記』です。
売上げ販売数は221万本となっています。
『遊戯王デュエルモンスターズ4 最強決闘者戦記』は、2000年12月7日にコナミからゲームボーイカラー用ソフトとして発売されたカードバトルゲームであり、当時爆発的な人気を誇っていた『遊☆戯☆王デュエルモンスターズ』シリーズのゲーム第4弾にあたります。
特筆すべきは、本作が“3バージョン同時発売”という形式を採っていた点で、それぞれ「城之内デッキ編」「海馬デッキ編」「遊戯デッキ編」という形で分かれており、収録カードや対戦相手の内容が異なる仕様となっていました。
このバージョン分けの手法は、1996年に登場した『ポケットモンスター赤・緑』の影響を色濃く受けたものであり、当時の小学生・中学生のあいだで「どのバージョンを買うか」という話題自体が一種のコミュニケーション手段となっていたこともあり、販促面でも大きな効果を上げました。
実際に、本作はゲームボーイカラー専用ソフトとしては異例の販売記録を樹立し、3バージョン合計で約220万本(国内)を売り上げ、当時のゲームボーイカラーソフトの中でもトップクラスのヒット作となりました。
ゲーム内容は、原作カードゲームをベースにしつつも、実際のOCG(公式カードゲーム)とはルールやカード効果が異なっており、あくまでゲーム独自のシステムが用いられている点が特徴です。
例えば、モンスターの召喚制限がゆるく、融合も素材カードを場に出す必要がないなど、テンポ重視のバトル展開が好まれていました。
その一方で、カードの入手手段がランダム性に依存しており、プレイヤーが欲しいカードを狙って集めることが難しかったことから、難易度の高さや育成要素の重さが一部で話題にもなりました。
また、本作には特典として限定OCGカードが同梱されており、「死のデッキ破壊ウイルス」など強力なカードがそれぞれのバージョンに封入されていたことも、コレクター心理を大きく刺激しました。
この限定カードの存在も、当時の販売数を大きく後押しした要因のひとつといえるでしょう。
『最強決闘者戦記』は、ゲームボーイカラー後期を代表する一本であると同時に、遊戯王ゲームシリーズの人気を決定づけた作品でもあります。
後の『封印されし記憶』や『TAG FORCE』シリーズなどに至るまで続く“遊戯王ゲーム文化”の礎として、今なお語り継がれる存在です。
8位:ドクターマリオ・・・208万本
| タイトル | ドクターマリオ |
| 発売日 | 1990年7月27日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 208万本 |
日本国内で8番目売れたゲームボーイ専用ソフトは『ドクターマリオ』です。
売上げ販売数は208万本となっています。
『ドクターマリオ』は、1990年7月27日に任天堂からファミコンとゲームボーイの同時発売でリリースされた落ち物パズルゲームであり、ゲームボーイ版はその携帯型向けバージョンとして展開されました。
当時すでに『テトリス』によって“落ちゲー”の面白さが広く知られ始めていた中で、任天堂独自のアレンジとキャラクター性を盛り込んだタイトルとして注目を集めました。
本作では、医者に扮したマリオ(通称「ドクターマリオ」)が、ビンの中に潜む3色のウイルスを「カプセル」と呼ばれるカラーブロックで消していくという独特の設定が採用されています。
プレイヤーは、2色に分かれたカプセルを縦または横に4つ以上並べて同色のウイルスを消す必要があり、その連鎖や先読みの組み立てが問われる、シンプルながら奥深いゲーム性が特徴です。
ゲームボーイ版においては、持ち運び可能な落ちゲーとして、当時の携帯型ゲーム市場に新たなジャンルを広げた立役者でもありました。
モノクロ表示ながら、ウイルスやカプセルは明確に区別できるよう工夫されており、視認性や操作性にも優れた作りになっています。
また、ゲームボーイ本体の通信ケーブルを用いた2人対戦プレイにも対応しており、友人との競争要素も強く、シンプルなルールながら非常に中毒性の高いタイトルとして長く親しまれました。
BGMにおいては、特に「FEVER」や「CHILL」といった曲が印象的で、軽快なテンポと耳に残るメロディはゲームの雰囲気を一層盛り上げる要素として高く評価されました。
とりわけ「FEVER」は後のスマブラシリーズなどでもアレンジされて登場し、ドクターマリオの象徴的なテーマとなっています。
『ドクターマリオ』は発売当初から高い人気を誇り、ゲームボーイ版単体でも国内外で大きな成功を収めました。
具体的な販売本数は公表されていないものの、任天堂の落ち物パズルとして確固たる地位を築き、以後もスーパーファミコン、N64、GBA、Wii、スマートフォンなど多機種に渡ってリメイク・続編が登場するなど、シリーズとして長く命脈を保ち続けています。
ゲームボーイ版はその原点にして、いまなお高い完成度を誇る作品として、任天堂パズルゲームの草分け的存在となっています。
9位:ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド・・・191万本
| タイトル | ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド |
| 発売日 | 1998年9月25日 |
| メーカー | エニックス |
| 国内販売数 | 191万本 |
日本国内で9番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』です。
売上げ販売数は191万本となっています。
『ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランド』は、1998年9月25日にエニックス(現スクウェア・エニックス)からゲームボーイ用ソフトとして発売された作品であり、人気RPG『ドラゴンクエスト』シリーズのスピンオフにして、モンスター育成・対戦型RPGの先駆けとも言える一本です。
当時すでに社会現象化していた『ポケットモンスター』に対抗すべく、”ドラクエの世界観で、モンスターを仲間にして戦わせる”ことを軸に企画されたこのタイトルは、結果的に独自の魅力を放ち、大ヒットを記録することとなりました。
本作の主人公は、のちに『ドラゴンクエストVI』に登場するテリーの幼少期の姿であり、姉のミレーユが謎の扉に吸い込まれたことをきっかけに、夢と現実が交差する不思議な世界”タイジュの国”へと足を踏み入れることになります。
プレイヤーは、さまざまな異世界(扉の中の世界)を巡りながらモンスターをスカウトし、育て、配合しながら最強のパーティを作り上げ、最終的には星降りの大会での優勝を目指すという流れになっています。
最大の特徴は、モンスター同士を掛け合わせて新たなモンスターを生み出す”配合”システムであり、これによって進化の系譜や育成の自由度が飛躍的に高められました。
単なるレベル上げだけではなく、戦略的な組み合わせや性格・特技の継承など、奥深い育成要素がプレイヤーの探究心を刺激し、”どの配合からどんなモンスターが生まれるのか”を試行錯誤する楽しみが、ゲームの大きな魅力のひとつとなりました。
また、登場モンスターは『ドラクエ』シリーズ歴代作品から数多く登場しており、ファンにとっては懐かしさと新鮮さが共存する内容となっていました。
さらに、通信ケーブルを用いた対戦・交換プレイにも対応しており、育てたモンスターを友達と戦わせる・譲り合うといった遊び方が強く推奨されていた点も当時の時代背景に合致しており、小中学生を中心に強い人気を集めました。
販売面においても極めて成功を収めており、国内出荷本数は約190万本を突破し、ゲームボーイ用ソフトの中でも屈指の大ヒットタイトルとして知られています。
その成功を受けて、『イルとルカの冒険』や『キャラバンハート』といった続編シリーズも展開され、のちにはニンテンドーDS・3DSでのリメイク版も登場するなど、長きにわたって愛され続けるシリーズの原点として、今なお高く評価されています。
『テリーのワンダーランド』は、ただのスピンオフ作品にとどまらず、”モンスターを仲間にして育てる”という楽しさを、ドラクエという土台に見事に融合させた名作であり、90年代末のゲームボーイ後期における代表的作品として、その名を刻んでいます。
10位:ポケットモンスター クリスタル・・・187万本
| タイトル | ポケットモンスタークリスタル |
| 発売日 | 2000年12月14日 |
| メーカー | 任天堂 |
| 国内販売数 | 187万本 |
日本国内で10番目に売れたゲームボーイ専用ソフトは『ポケットモンスター クリスタル』です。
売上げ販売数は187万本となっています。
『ポケットモンスター クリスタル』は、2000年12月14日にゲームボーイカラー専用ソフトとして任天堂から発売された作品で、『ポケットモンスター 金・銀』の内容をベースに、演出や遊びやすさを強化したマイナーチェンジ版として登場しました。
前作『金・銀』がゲームボーイソフトでありながらゲームボーイカラー対応だったのに対し、『クリスタル』はゲームボーイカラー専用タイトルとして、より多彩な色使いや細やかなアニメーション演出が加えられており、シリーズとしても初めて「カラー専用」と銘打たれたポケモン作品となります。
最大の特徴のひとつは、シリーズ初となる”女の子主人公の選択”が可能になったことで、それまで男性主人公のみだったプレイヤーキャラクターに対し、性別を選べるようになったことは、特に当時の女性プレイヤー層から大きな支持を集めました。
また、伝説のポケモン「スイクン」が物語の中心に据えられており、従来のようにプレイヤーの判断で出会うのではなく、ストーリーの中で特別な演出とともに登場するという演出が取り入れられたことも、ドラマ性を高める要素となっています。
その他にも、バトル開始時にポケモンがアニメーションで動く演出の導入や、施設「バトルタワー」の初登場、また通信機能の活用を前提としたイベント(携帯アダプタを使った通信配信など)など、金銀の基盤を活かしつつ、さまざまな改良が施されており、単なる完全版にとどまらない“もう一つのジョウト地方体験”として位置づけられています。
販売面においても好調な数字を記録し、国内では約187万本を売り上げ、当時としてはマイナーチェンジ版ながら非常に高い評価を得たことがわかります。
なお、同年は『ドラクエモンスターズ2』や『最強決闘者戦記』などライバルタイトルが並ぶ中で、なお強い存在感を放ったことも注目すべき点です。
『クリスタル』は、”シリーズの中間作=マイナーバージョン”が単なる調整版ではなく、演出・シナリオ・プレイ体験において独自の進化を遂げ得ることを証明した一本であり、その後に続く『エメラルド』『プラチナ』『ウルトラサン・ウルトラムーン』といった作品群に道を拓いた、先駆的なタイトルといえるでしょう。
ゲームボーイカラーの表現力を最大限に引き出したポケモン作品として、今なお多くのファンに愛される一作です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、ゲームボーイ及びゲームボーイカラー専用ソフトの国内販売数ランキングトップ10をご紹介しました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
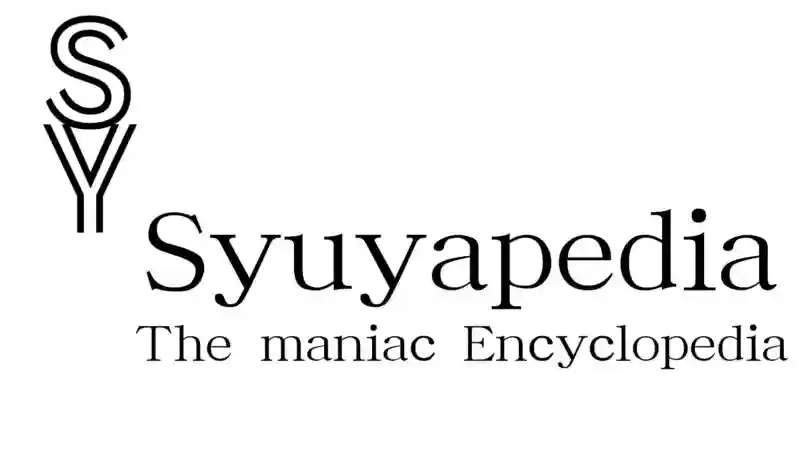





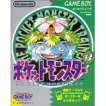

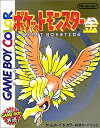
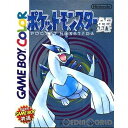
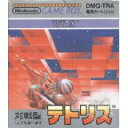
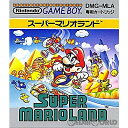





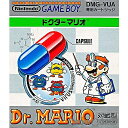
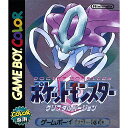


コメント