京都にある禅寺の内、室町幕府3代将軍足利義満によってつけられた”格付け”トップ5である”京都五山”と、その”別格”である南禅寺についてわかります。
みなさんこんにちは、syuyaです。
皆さんは禅寺と言われて、どこを思い浮かべますか?
そもそも禅寺とは、仏教の一派の内の大乗仏教の中で、中国で発祥し日本に伝わった禅宗の修行の為に建てられたお寺の事です。
そんな禅寺には、室町幕府3代将軍足利義満によって1386年に成された”格付け”があります。
東の鎌倉の禅寺5か所、西の京都の禅寺5か所を、それぞれ”鎌倉五山””京都五山”として、それぞれ1位~5位までの序列をつけたのでした。
こういう設定って、なんだか少年漫画の敵の組織の設定のようですよね。
わくわくするのは私だけではないはずです。
この記事ではその内”京都五山”を、順位が高い順からご紹介していきます。

京都旅行に行くなら、日本旅行の国内ツアーがおススメ
どこよりも安く快適なツアーが豊富にあり、京都の禅寺巡りにも最適です。
詳細は下のボタンをタップしてご覧ください。
第一位:天龍寺
osakaosaka – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=8767864による
京都五山の序列1位は、嵐山にある禅寺である天龍寺です。
創建年は1343年で、室町幕府初代将軍足利尊氏によって創建されました。
開山(初代住職)は夢窓疎石(むそうそせき)です。
第96代天皇であった後醍醐天皇が1339年に崩御した後、臨済宗の僧侶であった夢窓疎石(むそうそせき)に勧められ、足利尊氏が政敵であった後醍醐天皇を弔うために建てられたのが天龍寺です。
法堂の天井に描かれた巨大な雲龍図の他、国の指定名勝にも選ばれた庭園である曹源池庭園など、多くの見所があります。
京都市の中でも一大観光地である嵐山エリアにある事から観光スポットとしても人気で、連日多くの人々に足を運ばれています。
天龍寺ホームページ:https://www.tenryuji.com/
第二位:相国寺
Photo by 663highland, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=56938672による
京都五山の序列2位は、京都御所の北に位置する相国寺です。
創建年は1382年で、室町幕府3代将軍足利義満によって創建されました。
開山(初代住職)は夢窓疎石(既に入滅していたため名目上)です。
中国の明との勘合貿易を行い、室町幕府の全盛期を築いた3代将軍足利義満が、自身の邸宅であった花の御所の隣接地に禅寺を建てる事を発起したことから建造が開始されました。
臨済宗のお寺の特徴の一つである巨大な法堂ですが、この相国寺の法堂は現存する同種の法堂の中でも最古のものであり、1605年に再建されたものです。
明治まで歴代天皇が居住していた京都御所の北側というこれ以上ない立地に位置しており、当時の室町幕府3代将軍足利義満の権力の凄まじさを伺い知ることが出来ます。
京都五山の格付けを行った義満本人の命により建てられたお寺ですが、初代将軍である尊氏の建てた天龍寺よりも序列を上にする訳にはいかなかった為、京都五山の序列二位という事になりました。
相国寺ホームページ:https://www.shokoku-ji.jp/
第三位:建仁寺
663highland, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=38440887による
京都五山の序列3位は、祇園の花見小路を南に進んだところにある建仁寺です。
創建年は1202年で、鎌倉幕府2代将軍である源頼家によって創建されました。
開山(初代住職)は栄西です。
伝統ある京都の花街である祇園エリアに位置するこの禅寺は、京都最古の禅寺と言われています。
開山者である栄西は、中国大陸から日本に臨済宗を最初に伝えたとされる僧で、建仁寺はその栄西自身によって建てられました。
四方を通路で囲まれた日本庭園の中庭である潮音庭や、法堂の天上に描かれた双竜図などの見所があります。
京都の中心地である祇園からすぐにアクセスできるため、連日観光客にも人気の禅寺です。
建仁寺ホームページ:https://www.kenninji.jp/
第四位:東福寺
PlusMinus – Photo by PlusMinus, CC 表示-継承 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=1287907による
京都五山の序列第4位は、京都市東山区の東南端で、伏見稲荷で有名な伏見区と隣接する場所にある東福寺です。
創建年は1236年で、鎌倉時代初期の公家である九条道家によって建造されました。
開山(初代住職)は円爾(えんに)です。
”東福寺”の名称は奈良の有名なお寺である東大寺と興福寺から一文字ずつ取って名付けられました。
東福寺の特徴は”東福寺の伽藍面(がらんづら)”とも呼ばれる見事な伽藍堂群の他、庭園が位置する”洗玉澗(せんぎょくかん)”と呼ばれる渓谷に、”臥雲橋”、”通天橋”、”偃月橋”と呼ばれる3つの橋が架かる壮大な風景が特徴です。
また京都屈指の紅葉の名所として知られ、紅葉シーズンには多くの見物客が訪れます。
東福寺ホームページ:https://tofukuji.jp/
第五位:万寿寺
Drnakain – 投稿者自身による著作物, CC 表示-継承 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=39735500による
京都五山の序列5位は、東福寺と同じく京都市東山区にある万寿寺です。
創建年は1096年で、白河上皇によって建造されました。
創建当初は臨済宗の禅寺ではなく、天台宗系の浄土教のお寺でありましたが、1257年頃に当時の住職であった十地覚空と弟子の東山湛照が東福寺の住職であった円爾に帰依したため、臨済宗の禅寺となりました。
”京都五山”のお寺の内唯一一般公開されておらず、国の重要文化財である”鐘楼”を近くから眺める事が出来るのみとなっています。
その成り立ちと言い、”京都五山”の内でも少し特殊なお寺と言えますね。
別格:南禅寺
663highland – 投稿者自身による著作物, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7567257による SONY DSC
最後にご紹介するのは西の”京都五山”、そして東の”鎌倉五山”の上に位置する”別格の禅寺”である南禅寺です。
南禅寺は京都市左京区南禅寺福地町にある臨済宗南禅寺派の大本山のお寺です。
創建年は1291年で、第90代天皇である亀山天皇によって創建されました。
開山(初代住職)は無関普門(むかんふもん)です。
日本で最初に時の天皇の勅令により創建された勅願禅寺とされています。
伝承によると、南禅寺の位置する地域には度々妖怪が現れていましたが、臨済宗の僧であった無関普門がその地に赴き、静かに座禅を組んだ結果妖怪が退散した事から、亀山天皇が無関普門に南禅寺の開山を命じたと伝えられています。
その禅寺としての格は”別格”で、
・”京都五山第一位”の天龍寺
・”鎌倉五山第一位”の建長寺
の上に位置する”日本中の禅寺のさらに上に位置する禅寺”です。
境内には様々な文化遺産が存在し、法堂や方丈といった禅寺の建造物の他にも、滋賀県にある琵琶湖から流れる琵琶湖疎水を京都市内に運ぶ、明治期に建造された人工のレンガ造りの水路である水路閣や
水路閣
歌舞伎の演目の一つである”桜門五三桐(さんもんごさんのきり)”にて、天下の大泥棒石川五右衛門が登り、京都市内を眺め
絶景かな、絶景かな
[/word_balloon]と言ったとされる南禅寺の三門など、多くの見所があります。
663highland – 投稿者自身による著作物, CC 表示 2.5, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7567257による SONY DSC
この三門の上には有料で上ることが出来、石川五右衛門が眺めたとされる絶景を堪能することも出来ます。
”禅寺の中の禅寺”である南禅寺の境内で静かに座禅を組んで瞑想すれば、もしかしたら悟りの境地に辿り着くことが出来るかもしれませんね。
南禅寺ホームページ:https://www.nanzenji.or.jp/
まとめ
いかがだったでしょうか?
鎌倉時代から主に武士の間で親しまれ、現代でも我々日本人の考え方に深く根付いている”禅”の思想。
その”禅”の思想を教え継いできた禅寺の最高峰である”京都五山”と”南禅寺”を訪れる事で、日本人の思想の核となる部分に触れる事が出来るかもしれませんね。
京都を訪れた際は、是非立ち寄ってみてはいかがでしょうか?
ここまで読んでいただいてありがとうございました。
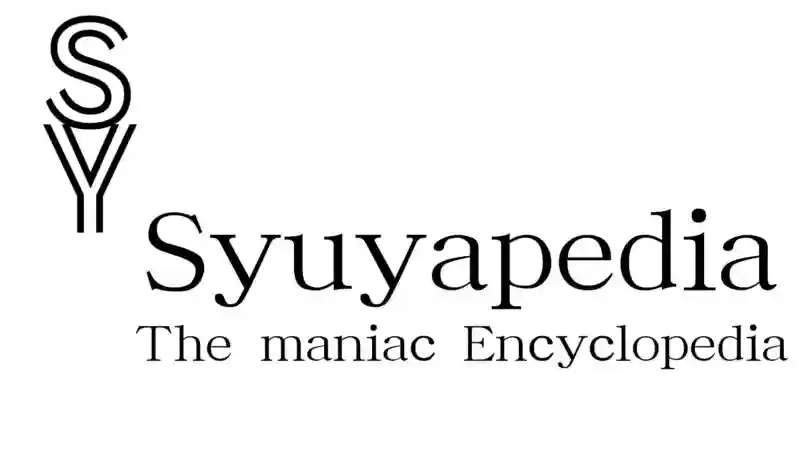










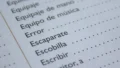
コメント