日本で発売された小説の、歴代発行部数ランキングトップ10の作品がわかります。
みなさんこんにちは、syuyaです。
この記事では、日本で発売された小説の内、発行部数の多い作品をご紹介しています。
日本の小説は、その発展の過程において独自の文学的伝統と社会的背景を反映してきました。
始まりを遡れば、平安時代の『源氏物語』や『枕草子』といった物語文学に至り、これらは世界的に見ても最古級の長編小説や随筆として位置づけられています。
これらは貴族社会を舞台とし、恋愛や人間関係の繊細な描写を通じて、後世の文学にも大きな影響を与えました。
江戸時代に入ると、庶民文化の隆盛とともに読本や草双紙、そして十返舎一九の『東海道中膝栗毛』など、娯楽性の強い作品が人気を博しました。
滑稽や風刺を織り交ぜた物語は、当時の社会を生きる人々の生活感や価値観を生き生きと伝え、識字率の高さを背景に広く読まれることとなります。
明治期に西洋文学が流入すると、日本の小説は大きな変革を迎えました。
二葉亭四迷が写実的な文体を用い、森鷗外や夏目漱石といった作家が近代小説の基礎を築きます。
彼らは西洋文学の形式を取り入れつつも、日本人の精神や社会の変化を表現し、日本独自の「私小説」というジャンルも生み出しました。
大正から昭和にかけては、芥川龍之介の知的で洗練された短編や、太宰治、川端康成といった作家の人間存在への深い洞察が文学の中心を成していきます。
戦後になると焼け跡からの復興や価値観の転換を背景に、大衆文学と純文学が並立して発展しました。
三島由紀夫の美学的な作品や遠藤周作の宗教的テーマは国際的にも注目され、やがて川端康成がノーベル文学賞を受賞したことで、日本文学は世界的評価を得るに至ります。
高度経済成長期以降は村上春樹のように現代的で国際感覚に富む作風が台頭し、日本の小説は国内にとどまらず広く翻訳され、グローバルな文学シーンの一翼を担うようになりました。
同時に、大衆小説やライトノベルといった娯楽的な作品群も拡大し、ベストセラーとして数百万部を売り上げる現象も珍しくなくなります。
こうした多様性は、かつての貴族文化に端を発した物語が、庶民、近代知識人、そして現代の大衆や世界の読者へと広がっていった、日本小説史の豊かな変遷を物語っています。
この記事では、そんな日本で発売された小説の歴代発行部数ランキングトップ10をご紹介しています。
※フィクション小説のランキングであるため、ノンフィクション作品はこの記事には含まれておりません。そして日本国内で売れた小説のランキングである為、海外の作家の作品も含まれます。なお発行部数などは資料によってばらつきがある為、絶対的な物ではありません。ご了承ください。
1位:ノルウェイの森・・・1300万部
| タイトル | ノルウェイの森 |
| 作者 | 村上春樹 |
| 発売日 | 1987年9月4日 |
| ジャンル | 青春恋愛小説 |
| 累計発行部数 | 1300万部 |
あらすじ
三十七歳になった主人公ワタナベ・トオルは、ビートルズの曲「ノルウェイの森」を耳にした瞬間、大学時代の青春の日々を回想し始めます。親友の自死による喪失感を抱える彼は、その死と深く関わる女性・直子と再会し、繊細で不安定な彼女と関係を築こうとします。しかし直子の心の闇は深く、やがて彼は自由で活力に満ちた緑とも出会い、二人の女性の間で揺れ動きます。愛と性、死と孤独が交錯する中で、若者が避けられない成長の痛みと、生きることそのものの意味が静かに問いかけられていきます。
『ノルウェイの森』は、村上春樹の作家活動における大きな転換点を示す作品です。
彼の初期作品では幻想性やポストモダン的な技巧が前景化していましたが、本作では徹底したリアリズムが選択され、より直接的に人物の心理や現実の人間関係が描かれています。
この手法の転換により、従来の読者層を超えて広範な支持を獲得し、結果的に社会現象的なベストセラーとなりました。
また、舞台となる一九六〇年代末は日本の学生運動が盛んだった時代であり、その社会背景の中で若者たちが抱えた不安や孤独感が物語に深い影を落としています。
作品全体に通底するのは「喪失」と「記憶」、そして「孤独と他者との関わり方」というテーマであり、村上文学に一貫して見られる問いかけが、より普遍的で切実な形で表現されています。
そのため『ノルウェイの森』は、村上春樹を世界的な作家へと押し上げる契機となっただけでなく、現代日本文学の中でも特別な位置を占める作品となっています。
2位:窓際のトットちゃん・・・800万部
| タイトル | 窓際のトットちゃん |
| 作者 | 黒柳徹子 |
| 発売日 | 1981年 |
| ジャンル | 児童文学、教育文学、エッセイ |
| 累計発行部数 | 800万部 |
あらすじ
小学校に入学したものの落ち着きがなく、教師から「この子は学校にいられません」と退学を言い渡された少女トットちゃんは、母親に連れられて「トモエ学園」という自由な校風の小学校に転入します。そこで出会う校長先生小林宗作の教育方針は、子どもの個性を尊重し、好奇心を伸ばすことを大切にするものでした。教室が電車の車両であったり、授業内容を子ども自身が選べたりするユニークな学びの場で、トットちゃんは伸びやかに成長していきます。戦争の影が差し込む時代背景を背にしながらも、子どもたちの明るさや学園生活の喜びが鮮やかに描かれています。
『窓ぎわのトットちゃん』は、単なる児童の成長物語にとどまらず、日本の教育観や子ども観に大きな一石を投じた作品です。
作者である黒柳徹子氏自身の幼少期を題材にしながら、トモエ学園で実践された自由で個性を尊重する教育の姿勢を描き出すことで、当時の日本の画一的な教育制度に対する強い対照となりました。
出版当時、日本は高度経済成長を経て社会全体が効率や均一性を重視する傾向にありましたが、この作品は「子どもは一人ひとり違っていい」という普遍的なメッセージを提示し、多くの読者に感動を与えました。
また、戦争という時代の記憶が作品の背景に流れており、教育が子どもの人生にどれほど大きな意味を持つかが強調されています。
児童文学として親しみやすくありながら、教育書としての価値や社会的な意義を兼ね備えており、日本の出版史における画期的な一冊といえるでしょう。
3位:こころ・・・750万部
| タイトル | こころ |
| 作者 | 夏目漱石 |
| 発売日 | 1914年 |
| ジャンル | 近代文学、心理 |
| 累計発行部数 | 750万部 |
あらすじ
物語は「先生」と呼ばれる人物と「私」との交流を軸に展開します。大学生である「私」は、鎌倉の海岸で偶然出会った「先生」に強く惹かれ、やがて東京で親しく交流するようになります。「先生」は人付き合いを避け、謎めいた孤独な生を送っていましたが、「私」はその内面に何か深い秘密があることを感じ取ります。物語が進むにつれ、「私」の父の死や時代の変化が重なり、ついに「先生」から長い遺書が「私」に宛てられます。その手紙には、かつての友人「K」との三角関係や裏切り、そしてそれに続く「K」の死に対する深い罪の意識と絶望が綴られており、「先生」が生涯を孤独に生きざるをえなかった理由が明らかにされていきます。
『こころ』は、明治から大正へと時代が移り変わるなかで、人間の心の奥底に潜む孤独や罪悪感、そして愛と死の問題を鋭く描いた作品です。
特に「先生」が抱える友人「K」との葛藤と罪の意識は、近代日本人が直面した倫理的・精神的な危機を象徴しているといえます。
また、作品の副題に「先生と私」とあるように、漱石は近代社会における「個人」と「他者」の関係性を深く問い直しました。
近代化とともに共同体的な価値観が崩れ、個人の内面が強く意識されるようになった大正期に、この小説はまさにその「近代の孤独」を描き出したのです。
文学的には淡々とした一人称の語りを通じて心理の揺らぎを描き出す手法が特徴的で、後の日本文学に大きな影響を与えました。
『こころ』は単なる恋愛悲劇を超え、日本近代文学が普遍的なテーマに到達した象徴的な作品であり、今なお世代を超えて読み継がれる理由もそこにあります。
4位:人間失格・・・713万部
| タイトル | 人間失格 |
| 作者 | 太宰治 |
| 発売日 | 1948年7月25日 |
| ジャンル | 近代文学、私小説 |
| 累計発行部数 | 713万部 |
あらすじ
物語は「はしがき」「第一の手記」「第二の手記」「第三の手記」、そして「あとがき」という形式で構成されています。主人公大庭葉蔵の手記という形で描かれる彼の人生は、幼少期から人間関係にうまく適応できず、周囲と隔絶感を抱いてきた姿に始まります。彼は「道化」を演じることで人々に受け入れられようとする一方で、内心では絶えず「人間」という存在に対する恐怖と不信を抱え続けます。やがて酒や薬物、女に溺れるようになり、自己崩壊の道を歩んでいく彼の姿は、戦後日本の混乱と重ね合わされながら徹底的な孤独を映し出します。最終的に葉蔵は「自分はもはや人間ではない」と結論づけ、社会から完全に逸脱していくさまが描かれています。
『人間失格』は、太宰治の生涯と深く結びついた自伝的色彩の濃い作品であり、いわゆる「私小説」の極点に位置するといえます。
葉蔵の告白的な筆致には、太宰自身の生きづらさや破滅的な衝動が色濃く反映されており、作品発表の直前に太宰が入水自殺を遂げたこともあって、その内容は「作者の遺書」ともみなされてきました。
文学的には、個人の疎外感や存在不安を極端なまでに突き詰めることで、近代社会における「人間とは何か」という普遍的な問いを提起しています。
そのため本作は単なる一作家の悲劇的自叙伝を超えて、現代人にも響く切実なテーマを抱え続けています。
日本の読者だけでなく、翻訳を通じて海外でも強い共感を呼び、文学的評価と同時に文化的アイコンともなった稀有な作品です。
5位:星の王子さま・・・600万部
| タイトル | 星の王子さま |
| 作者 | アントワーヌ・ド・サン=テグジュペリ |
| 発売日 | 1953年(日本語訳版) |
| ジャンル | 寓話、児童文学、哲学的文学 |
| 累計発行部数 | 600万部 |
あらすじ
物語は、砂漠に不時着した飛行士である「ぼく」が、小さな星からやってきた「王子さま」と出会う場面から始まります。王子さまは、自分の星に残してきた一本のバラを大切に思いながらも、他の星々を旅してさまざまな大人たちと出会ってきた体験を語ります。権力にとらわれる王様、虚栄心に支配された男、数字にしか興味のない実業家、決まりを守るためだけに働く点灯夫など、それぞれが人間社会を風刺する存在として描かれます。最終的に王子さまは地球にやってきて、キツネとの出会いを通じて「本当に大切なものは目に見えない」という真理を学びます。そして王子さまは自分の星へ戻る決意を固め、「ぼく」に別れを告げるのです。
『星の王子さま』は、表面的には児童向けの童話でありながら、その内実は人生の本質を探る寓話であり、哲学的な奥行きを備えた普遍的な物語です。
砂漠に不時着した飛行士という語り手の設定には、サン=テグジュペリ自身が飛行士であった経歴が色濃く反映されており、実存的な孤独や人間関係の儚さが物語の背景に漂っています。
王子さまが出会う数々の大人たちは、人間が成長する過程で失ってしまう純粋さや想像力を象徴しており、彼らの姿を通じて現代社会に対する批評がなされています。
また、キツネが語る「大切なものは目に見えない」という言葉は、作品の核心であり、友情や愛、責任といった目に見えない価値の重要性を訴えています。
第二次世界大戦中という不安定な時代に生まれた本作は、人間の本質を問い直す作品として、国境や時代を超えて読み継がれています。
世界では約2億部が売れ、世界で9番目に売れた作品となっています。
日本においても戦後まもなく翻訳が広まり、子どもから大人まで幅広い層に愛される永遠の名作となっています。
6位:永遠の0・・・546万部
| タイトル | 永遠の0 |
| 作者 | 百田尚樹 |
| 発売日 | 2006年8月23日 |
| ジャンル | 歴史小説、戦争文学、家族小説 |
| 累計発行部数 | 546万部 |
あらすじ
物語は、司法試験に落ち続けている青年・佐伯健太郎とその姉慶子が、祖母の死をきっかけに、祖父の人物像を調べ始めるところから始まります。彼らが探し求める祖父・宮部久蔵は、零戦の優れた操縦士として知られながらも「臆病者」と呼ばれていた人物でした。調査を進めるうちに、健太郎と慶子は、宮部が徹底して「生きて帰ること」にこだわっていた理由や、彼が周囲から誤解され孤立していった過程を知ることになります。そして、彼がただ家族のもとへ帰るために必死で生き延びようとしながらも、最終的に特攻隊として命を散らすに至った真実が浮かび上がっていきます。
『永遠の0』は、戦争という巨大な悲劇の中で個人がどのように生き、そして死を迎えたのかを真正面から描いた作品です。
特攻隊という題材は、長らく日本社会で賛否が分かれるテーマでしたが、本作では「死を美化する」側面よりも、むしろ「生きたい」という人間の根源的な願いと、その願いを押し潰す戦争の非情さが描かれています。
宮部久蔵という人物像は、勇敢であると同時に臆病であり、英雄であると同時に弱さを抱えた人間として造形されており、読者はその二重性に強く心を揺さぶられます。
また、現代の若者である健太郎と慶子の視点を通して戦争を振り返る構成は、世代を超えて戦争の記憶をつなぐ役割を果たしており、日本社会における歴史認識や戦争の記憶のあり方に一石を投じました。
文学的価値と同時に大衆性も備え、平成の戦争文学を代表する作品として位置づけられています。
7位:ハリー・ポッターと賢者の石・・・506万部
| タイトル | ハリー・ポッターと賢者の石 |
| 作者 | J.K.ローリング |
| 発売日 | 1999年12月8日 |
| ジャンル | ファンタジー、児童文学 |
| 累計発行部数 | 506万部 |
あらすじ
物語は、ロンドン郊外で冷たく扱われている孤児の少年ハリー・ポッターが主人公です。親戚の家で冷遇されていた彼は自身が魔法使い(ウィザード)であることを知らされ、魔法使いを育てる特別な学校であるホグワーツ魔法魔術学校へ入学する手紙を受け取ります。そこで彼は親しい友人ロン・ウィーズリーやハーマイオニー・グレンジャーと出会い、学校に隠された謎に挑むことになります。彼らは「賢者の石」を巡る陰謀に気づき、暗黒の魔法使いヴォルデモート卿が復活を企てていることを知ります。ハリーは友人たちと協力し、危機を回避しながら自分の出生の秘密と宿命に向き合っていきます。
『ハリー・ポッターと賢者の石』は、児童文学の枠を超えて世界中の読者を魅了した、ポスト『児童書』の象徴的作品です。
魔法学校ホグワーツという独創的な舞台設定と、友情・勇気・成長といった普遍的なテーマを織り交ぜた物語は、子どもから大人まで幅広い層に支持されました。
その豊かな想像力と軽快な文体は、読者を見知らぬ世界へ引き込みつつ、現代の社会問題や価値観にもさりげなく触れています。
シリーズ全体は翻訳版を含め世界中で6億部以上を売り上げており、単なるベストセラーではなく、 現代の文化的現象 として位置づけられています。
ハリー・ポッターシリーズは日本でも大ヒットシリーズとなり、第一巻である『ハリー・ポッターと賢者の石』は506万部を売り上げ歴代小説で7番目に売り上げる結果となりました。
8位:老人と海・・・499万部
| タイトル | 老人と海 |
| 作者 | アーネスト・へミングウェイ |
| 発売日 | 1953年 |
| ジャンル | 近代文学、冒険小説、寓話文学 |
| 累計発行部数 | 499万部 |
あらすじ
舞台はキューバの小さな漁村。主人公は老漁師サンチャゴで、84日間も魚が一匹も釣れない不運な日々を過ごしていました。彼は村人たちから同情や嘲笑を受けつつも、もう一度大きな魚を仕留めるために小舟で沖へ出ます。そこで彼は巨大なカジキと遭遇し、孤独な戦いを繰り広げます。数日間にわたりサンチャゴは肉体的にも精神的にも極限状態となりながら魚と格闘し、ついにカジキを仕留めることに成功します。しかし帰路の途中でサメに襲われ、苦労して得た獲物は骨だけとなってしまいます。満身創痍で村へ戻ったサンチャゴは、何も残せなかったにもかかわらず、その壮絶な戦いを通して不屈の精神を示し、村人たちに畏敬を抱かせるのでした。
『老人と海』は、単なる漁師の冒険譚を超えて、人間の誇りと孤独、自然との対峙、そして敗北と尊厳という普遍的なテーマを描いた寓話的作品です。
ヘミングウェイ特有の簡潔で力強い文体「アイスバーグ理論」が際立ち、表面的な描写の奥に深い象徴性が込められています。
老漁師サンチャゴは人間の限界に挑む存在として描かれ、彼の戦いは読者にとって「人生そのものの縮図」として映ります。
たとえ結果が敗北であっても、その過程に宿る勇気と気高さが尊重されるというメッセージは、戦後の不安定な時代に強く響き、今日でも読み継がれています。
『老人と海』はヘミングウェイ文学の集大成であると同時に、世界文学の金字塔ともいえる作品です。
9位:坊ちゃん・・・438万部
| タイトル | 坊ちゃん |
| 作者 | 夏目漱石 |
| 発売日 | 1906年4月1日 |
| ジャンル | 近代文学、教養小説、ユーモア文学 |
| 累計発行部数 | 438万部 |
あらすじ
東京で生まれ育った快活で短気な青年「坊ちゃん」は、数学教師として四国の松山にある中学校に赴任します。まっすぐで曲がったことが嫌いな坊ちゃんは、赴任先の学校で、ずる賢く立ち回る教員や裏表のある同僚、さらに生徒たちのいたずらに直面します。学校内では「赤シャツ」と呼ばれる教頭と、「野だいこ」とあだ名される腰巾着的な教師が勢力を握っており、彼らの欺瞞や卑劣な振る舞いに対して坊ちゃんは真っ向から立ち向かいます。最終的に坊ちゃんは正義感に従って痛快な行動を取り、同僚の山嵐と協力して彼らを懲らしめたのち、教師生活を潔く去って東京へ戻ることを選びます。
『坊ちゃん』は、明治という近代化の時代背景の中で、理不尽や偽善に対する青年の直情的な反抗を描いた痛快な青春小説です。
主人公の無鉄砲さや率直さは滑稽さを帯びつつも、読者に強い共感と爽快感を与え、同時に社会の矛盾や人間関係の複雑さを浮き彫りにします。
漱石の文体は、江戸的な洒脱さと西洋的な小説形式が融合したものであり、口語的なユーモアに満ちた語り口は当時の読者に新鮮な驚きをもたらしました。
また、坊ちゃんと故郷に残した下女・清の交流は、作中に温かさと人間味を添える重要な要素です。
単なる勧善懲悪の物語ではなく、人間の愚かしさと誠実さを同時に描き出すことで、今なお広く読み継がれ、日本の国民文学と呼ぶにふさわしい作品となっています。
10位:ハリーポッターと秘密の部屋・・・433万部
| タイトル | ハリー・ポッターと秘密の部屋 |
| 作者 | J.K.ローリング |
| 発売日 | 2000年9月19日 |
| ジャンル | ファンタジー、児童文学 |
| 累計発行部数 | 433万部 |
あらすじ
ホグワーツ魔法魔術学校の2年生となったハリー・ポッターは、夏休みを意地悪なダーズリー家で過ごしていました。そんなハリーのもとに屋敷しもべ妖精ドビーが現れ、「ホグワーツへ戻ってはならない」と警告します。ハリーはその忠告を無視し、親友ロンやハーマイオニーと再び学園生活を始めますが、校内では次々と生徒が石化する怪事件が発生します。やがて「秘密の部屋」と呼ばれる伝説の場所の存在が浮かび上がり、恐るべき怪物が解き放たれたことが判明します。ハリーは「秘密の部屋」を探しつつ、恐るべき怪物とその背後に潜む黒幕と対峙します。
『秘密の部屋』はシリーズ第2作として、物語のスケールを広げながらハリーの出生やヴォルデモートとの因縁をより深く描き出した作品です。
学園内に潜む恐怖や血統主義をめぐる対立などが浮き彫りにされ、単なる冒険譚から社会的寓意を帯びた物語へと展開していきます。
また、ドビーやジニー・ウィーズリー、そしてトム・リドルといった新たな人物が登場し、後のシリーズ全体に大きな影響を及ぼす基盤が築かれました。
恐怖や謎解きの要素が強調されている一方で、ユーモアや友情の物語としての魅力も健在であり、児童文学でありながら幅広い年齢層に楽しめる普遍性を持っています。
『秘密の部屋』は、シリーズが単なる一過性の人気ではなく、継続的な世界的現象へと発展していくことを示した重要な一冊といえるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、日本で発売された小説の発行部数ランキングトップ10をご紹介しました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
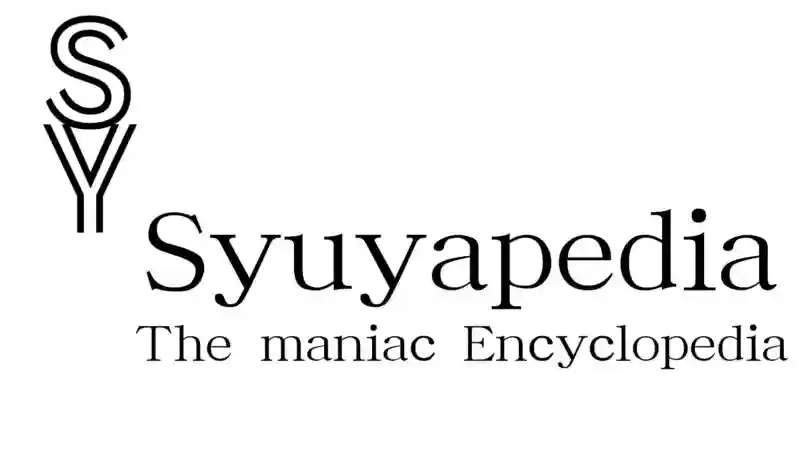
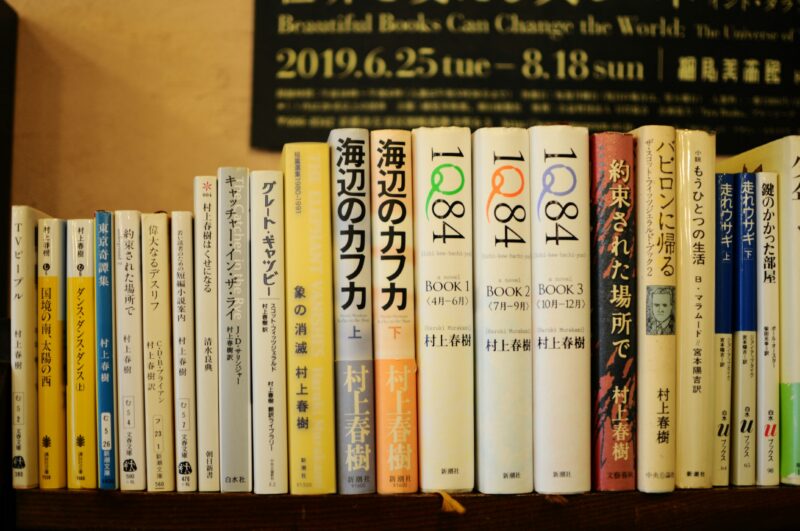
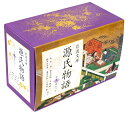













コメント