ドラゴンクエストシリーズの、国内売上ランキングトップ10が分かります。
『ドラゴンクエスト』シリーズは、1986年に第1作がファミリーコンピュータ向けに発売されて以来、日本のロールプレイングゲーム(RPG)の草分け的存在として、長きにわたり多くのファンに愛され続けている国民的ゲームシリーズです。
企画・シナリオを堀井雄二、キャラクターデザインを鳥山明、音楽をすぎやまこういちという3人のクリエイターが担う“黄金トリオ”によって作られたことで知られ、シンプルながら奥深いゲーム性と、誰もが共感できる王道のストーリー展開が特徴です。
初期作では世界を旅しながら魔王を倒すという明快な目的のもと、村人との会話やダンジョン探索を通して物語が進行していく、純粋な冒険譚が描かれていました。
その後もシリーズを重ねるごとに、キャラクター同士の人間ドラマ、過去と未来を巡る壮大な時間軸、善悪を超えた視点で描かれる深いテーマなどが盛り込まれ、ただの勇者物語にとどまらない厚みのある作品群へと成長しています。
ゲームシステムは、ターン制コマンドバトルを基礎に据えつつも、転職やスキルポイント、モンスター育成、仲間AI操作、通信機能など、時代に合わせた革新を取り入れてきました。
中でも『ドラゴンクエストⅢ』の職業システムや、『ドラゴンクエストⅤ』の仲間モンスター、『ドラゴンクエストⅨ』のすれちがい通信、『ドラゴンクエストⅪ』の美麗なグラフィックと語り口は、その時代のゲーム文化に大きな影響を与えました。
シリーズはナンバリング作品のほかにも、多くの外伝作品やスピンオフが展開されており、例えば『トルネコの大冒険』や『ドラゴンクエストモンスターズ』シリーズは、独自のジャンルとファン層を築いています。
またアニメや映画、小説、舞台などメディアミックスも盛んで、ゲームを超えた文化的存在として根付いています。
この記事ではそんなドラゴンクエストシリーズの内、国内売上販売数ランキングトップ10の作品をご紹介します。
- 1位:ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人(DS)・・・437万本
- 2位:ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち(PS)・・・417万本
- 3位:ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ(FC)・・・380万本
- 4位:ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君(PS2)・・・361万本
- 5位:ドラゴンクエストⅪ過ぎ去りし時を求めて(3DS・PS4)・・・360万本
- 6位:ドラゴンクエストⅥ 幻の大地(SFC)・・・320万本
- 7位:ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち(FC)・・・304万本
- 8位:ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁(SFC)・・・280万本
- 9位:ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々(FC)・・・240万本
- 10位:ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁(PS2)・・・161万本
- まとめ
1位:ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人(DS)・・・437万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人 |
| ゲームハード | ニンテンドーDS |
| 発売日 | 2009年7月11日 |
| 国内販売数 | 437万本 |
日本国内で最も売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人』です。
国内販売数は437万本となっています。
『ドラゴンクエストⅨ 星空の守り人』は、2009年7月11日にニンテンドーDS専用ソフトとして発売された、ドラゴンクエストシリーズのナンバリング第9作目です。
シリーズ初となる携帯ゲーム機向けタイトルとして登場し、その新機軸の数々が大きな話題を呼びました。プレイヤーは“天使”として人間たちを見守る存在でしたが、ある出来事を境に地上に堕ち、記憶と力を失った状態で、人間の世界で新たな使命と運命に立ち向かうことになります。
本作のストーリーは従来の直線的な構成とはやや異なり、各地を巡るオムニバス形式のエピソードを中心に展開されます。
プレイヤーは様々な人々の物語に触れながら、次第にこの世界を脅かす大きな陰謀と、天使の使命の真実に迫っていきます。
感動的なドラマと緻密な構成、そして道中で描かれる人々の葛藤や救済の物語は、シリーズならではの深みを感じさせる内容となっています。
システム面では、シリーズ初の本格的なキャラクターカスタマイズ要素が導入されており、プレイヤーキャラクターの見た目や装備が自由に変更できるようになっています。
職業システムも復活し、戦士・僧侶・魔法使いなどの基本職に加え、上級職も多数用意され、成長の幅が広がりました。
また戦闘にはスキルポイント制やテンションシステムが加えられ、戦略性と爽快感を両立させたバトルが楽しめます。
特筆すべきはDSの通信機能を活用した「すれちがい通信」や「Wi-Fi通信」による要素で、他プレイヤーとのキャラ交換や宝の地図の共有、さらには配信クエストの受信など、オンラインとオフラインが融合した遊び方が可能となりました。
特に宝の地図のダンジョン探索はやり込み要素として非常に高く評価され、レアアイテムや強敵とのバトルを求めて何百時間もプレイするユーザーも少なくありませんでした。
開発はレベルファイブが担当し、堀井雄二・鳥山明・すぎやまこういちの三名が引き続き制作に関わっています。
ドラクエらしさを継承しつつも、新しい世代に向けて大きく刷新された本作は、シリーズの中でも異色でありながら高い完成度を誇るタイトルとなりました。
販売本数は国内で約437万本を記録したことから、当時のDS市場を牽引するビッグタイトルのひとつとして現在でも語り継がれています。
2位:ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち(PS)・・・417万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち |
| ゲームハード | PlayStation |
| 発売日 | 2000年8月26日 |
| 国内販売数 | 417万本 |
日本国内で2番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち』です。
国内販売数は417万本となっています。
『ドラゴンクエストⅦ エデンの戦士たち』は2000年8月26日にプレイステーション向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズの第7作目にあたるナンバリングタイトルです。
2Dから3Dへの過渡期にあたるこの時代に、シリーズで初めてフル3Dのフィールドを採用しながらも、従来のコマンドバトルやメニュー構造など、ドラクエらしさを丁寧に守った作品として高く評価されました。
プレイヤーは小さな島国「エスタード島」で静かな日常を過ごす少年として冒険を始め、石版によって過去の世界に飛び、失われた土地や文明を少しずつ復活させていくという、独特かつ壮大な構成が本作の最大の特徴です。
本作のシナリオは非常に重厚で、プレイヤーが各地の過去を巡ることで、世界の秘密とそれぞれの土地に起きた悲劇、人間の愚かさや希望を目の当たりにしていくという内容になっています。
1つ1つのエピソードが独立していながらも、全体として密接に絡み合い、やがて一つの大きな物語へと収束していく構成は、シリーズでも随一のスケールと緻密さを誇ります。
ゲームシステムでは前作『ドラゴンクエストⅥ』で好評だった職業システムがさらに進化し、多彩な職業と転職を通じてキャラクターを自由に育成できる点が魅力です。
また戦闘では新たに「モンスターの心」を用いた職業も追加され、プレイスタイルの幅が大きく広がりました。
膨大なボリュームを誇り、クリアまでに100時間を超えるプレイ時間がかかることも珍しくない本作は、じっくりと腰を据えて遊ぶタイプのRPGとして根強い支持を集めました。
グラフィックは、ポリゴンで描かれたフィールドと2Dスプライトのキャラクターという混合スタイルを採用し、当時としては先進的でありながらもドラクエらしい親しみやすさを残しています。
音楽はもちろんすぎやまこういちによるもので、重厚なテーマから郷愁を誘う旋律まで、物語の世界観を豊かに彩っています。
発売当時はPlayStationという新たなプラットフォームでの展開とあって大きな注目を集め、販売本数は国内だけで400万本以上を記録しました。
その後、2013年にはニンテンドー3DS向けにフルリメイクも行われ、現代のプレイヤーにもその物語の魅力が受け継がれています。
『ドラゴンクエストⅦ』は物語性の深さと圧倒的なボリュームで、シリーズにおける異色作かつ傑作として、今も多くのファンの記憶に残る一本です。
3位:ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ(FC)・・・380万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ |
| ゲームハード | ファミリーコンピュータ |
| 発売日 | 1988年2月10日 |
| 国内販売数 | 380万本 |
日本国内で3番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ』です。
国内販売数は380万本となっています。
『ドラゴンクエストⅢ そして伝説へ…』は、1988年2月10日にファミリーコンピュータ向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズの第3作目です。
本作はシリーズの中でも特に高い人気と評価を誇り、「RPGの金字塔」とも称される伝説的な作品です。
プレイヤーは勇敢な父オルテガの遺志を継いだ16歳の主人公として世界を旅し、大魔王バラモス、そしてその先に待つ真の黒幕と対峙していく壮大な冒険へと旅立ちます。
本作は、自由度の高さとゲーム性の進化が大きな特徴です。
プレイヤーは最初に仲間を自由に作成・編成でき、戦士、僧侶、魔法使い、盗賊、商人、遊び人など、さまざまな職業を選ぶことができます。
さらに成長とともに転職が可能になり、キャラクターの育成戦略に大きな幅が生まれました。
この職業システムは後のシリーズにも大きな影響を与え、RPGジャンル全体においても画期的な要素とされました。
物語の舞台となるのは「アリアハン」を中心とした広大な世界で、各地には個性豊かな町や村、ダンジョンが存在し、それぞれに異なる文化や問題が描かれています。
旅の途中で出会う人々との交流、困難を乗り越える過程、そして終盤に明かされる意外な真実が、物語に大きな深みを与えています。
特に物語の終盤で舞台が前作『ドラゴンクエストⅠ・Ⅱ』の世界へとつながる展開は、当時のプレイヤーに大きな驚きと感動を与えました。
戦闘はコマンド選択式のターン制で、シンプルながら緊張感があり、戦略的なパーティ編成や魔法の使いどころが勝敗を分けます。
またレベルアップや装備の充実、モンスターとの戦いを通じて着実に成長を実感できる点も、RPGの王道としての魅力を支えています。
音楽はすぎやまこういちによる荘厳なメロディが全編にわたり流れ、冒険の雰囲気を情感豊かに盛り上げています。
発売当時は社会現象と呼ばれるほどの熱狂ぶりで、発売日の早朝から長蛇の列ができ、学校を休んでゲームを買いに行く子どもたちの姿がニュースになるほどでした。
その後もスーパーファミコンやゲームボーイカラー、スマートフォンなどに移植・リメイクされ、世代を超えて多くのプレイヤーに親しまれています。
『ドラゴンクエストⅢ』はシリーズの原点を締めくくる“ロト三部作”の完結編として、そしてRPG史に残る名作として、今なお色あせることのない輝きを放っています。
4位:ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君(PS2)・・・361万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君 |
| ゲームハード | PlayStation2 |
| 発売日 | 2004年11月27日 |
| 国内販売数 | 361万本 |
日本国内で4番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君』です。
国内販売数は361万本となっています。
『ドラゴンクエストⅧ 空と海と大地と呪われし姫君』は2004年11月27日にプレイステーション2向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズ第8作目のナンバリングタイトルです。
本作はシリーズで初めてキャラクターやフィールド、町並みに至るまで完全な3Dグラフィックで描かれ、従来の“ドット絵”の世界観から大きく進化を遂げた作品として知られています。
美しい自然、広大なフィールド、滑らかに動くキャラクターたちが織りなす世界は、まさに“冒険そのもの”を体感できる革新的なRPGとなりました。
プレイヤーはある呪いによって姿を変えられた王様と姫君を救うため、王国の兵士である主人公として旅を始めます。
やがて物語は邪悪な魔法使いドルマゲスとの対決、古代文明の謎、そして世界の命運を賭けた壮大な戦いへと発展していきます。
キャラクターの感情や関係性が丁寧に描かれており、仲間たちの個性や成長を強く感じられる点も、本作ならではの魅力です。
ゲームシステム面では「スキルポイント制」が導入され、レベルアップごとに得られるポイントを自由に振り分けることで、各キャラクターの成長方向をプレイヤーが決定できるようになりました。
武器の選択によって覚える特技が異なり、戦略性と自由度の両立が実現されています。
またバトルはシリーズ伝統のコマンド制ながらも、モンスターや仲間キャラがリアルタイムで動く演出が加わり、視覚的な迫力が格段に向上しました。
フィールド探索においては、馬車での移動やモンスターとの遭遇、アイテム探索など、3D空間を活かした仕掛けが多く盛り込まれ、旅そのものを楽しめる設計がなされています。
さらに「錬金釜」を使ってアイテムを調合する要素や、「モンスター・バトルロード」といったサブコンテンツも充実しており、やり込み要素の面でも非常に高い評価を受けました。
開発はレベルファイブが担当し、堀井雄二・鳥山明・すぎやまこういちの黄金トリオが引き続き参加。
フルボイス対応、オーケストラ音源採用といった豪華な演出により、物語の没入感も飛躍的に向上しました。
販売本数は国内で350万本を超え、全世界累計では500万本以上を記録する大ヒットとなり、シリーズの新たな時代を切り拓いた象徴的な作品となっています。
その後もニンテンドー3DS版としてリメイクが行われ、新たな仲間キャラやイベント、利便性の向上などが加えられたことで、現代のプレイヤーにも再評価されています。
『ドラゴンクエストⅧ』は、“見て、聞いて、触って”楽しめるRPGとして、シリーズにおける大きな転換点でありながら、原点である“王道の冒険”をしっかりと貫いた傑作として、今なお色褪せることのない魅力を放ち続けています。
5位:ドラゴンクエストⅪ過ぎ去りし時を求めて(3DS・PS4)・・・360万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅪ過ぎ去りし時を求めて |
| ゲームハード | PlayStation4、ニンテンドー3DS |
| 発売日 | 2017年7月29日 |
| 国内販売数 | 360万本 |
日本国内で5番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』です。
国内販売数は360万本となっています。
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』は2017年7月29日にPlayStation 4およびニンテンドー3DS向けに同時発売された、シリーズのナンバリング第11作目です。
シリーズ誕生から30周年の節目に登場した本作は「新たな原点」として開発され、最新技術を取り入れながらも、これまでのドラゴンクエストが大切にしてきた“王道の冒険”と“感動の物語”を高い完成度で描き出した作品です。
プレイヤーは「勇者の生まれ変わり」として生を受けた青年を操作し、広大な世界「ロトゼタシア」を舞台に、運命に導かれながら旅をしていきます。
やがて彼は“勇者=災いをもたらす存在”として追われる立場となり、仲間たちと出会いながら、自身の宿命と世界の真実に向き合っていくことになります。
物語は王道ながらも巧みに練られた構成で、後半には予想を超える大きな展開と、プレイヤーの感情を揺さぶる選択が待ち受けています。
システム面ではPlayStation 4版は美しい3Dグラフィックと広大なフィールド探索を特徴とし、3DS版では上下2画面を活かして3Dと2Dドット表示を切り替えられるという、シリーズファンに嬉しい仕様が導入されました。
さらに2019年には、ボイス対応やオーケストラ音源、新ストーリーなどを追加した『ドラゴンクエストXI S 過ぎ去りし時を求めて』がNintendo Switch向けに発売され、後に他機種にも展開されました。
戦闘は伝統のターン制コマンドバトルを継承しながらも、「れんけい技」やキャラクターごとの特技、スキルパネルによる成長システムなど、現代的な遊びやすさと戦略性が両立されています。
またパーティメンバーはいずれも強烈な個性と深い人間性を持ち、彼らとの絆が物語をより豊かに彩っています。
中でもセーニャ、カミュ、ベロニカ、シルビアといった仲間たちは、多くのファンの心に深い印象を残しました。
音楽はすぎやまこういちによる新曲と過去作の名曲を交えた構成となっており、旅の情景や物語の節目を美しく盛り上げています。
またシリーズ初となる「時を超える物語」の要素が盛り込まれており、過去シリーズへの敬意と繋がりが随所に感じられる構成は、長年のファンにとって感慨深いものとなっています。
販売面でも高い評価を受け、日本国内では300万本以上を売り上げ、全世界累計出荷本数は700万本を超える大ヒットを記録しました。
ゲーム業界内外からの受賞も多数受け、まさにシリーズの集大成としてふさわしい評価を獲得しています。
『ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて』は、シリーズの伝統と革新の融合を体現した傑作として、多くのプレイヤーの心に深く刻まれる冒険となりました。
6位:ドラゴンクエストⅥ 幻の大地(SFC)・・・320万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅥ 幻の大地 |
| ゲームハード | スーパーファミコン |
| 発売日 | 1995年12月9日 |
| 国内販売数 | 320万本 |
日本国内で6番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅥ 幻の大地』です。
国内販売数は320万本となっています。
『ドラゴンクエストⅥ 幻の大地』は、1995年12月9日にスーパーファミコン向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズのナンバリング第6作目です。
“天空シリーズ”三部作の完結編にあたる本作は、現実と幻、表と裏という二重世界を舞台に、自己の存在意義をめぐる深いテーマと、重厚なシナリオが大きな特徴となっています。
プレイヤーはある村の若者として旅を始めますが、やがて自分の記憶や過去に隠された真実、そして世界の成り立ちに迫る壮大な物語へと巻き込まれていきます。
物語は「現実世界」と「幻の世界(夢の世界)」という、二つの世界を行き来しながら進行します。
各世界で起こる出来事が互いに影響し合っており、両方を探索しながら謎を解き明かしていく構成は、シリーズでも特に複雑で奥行きのある展開となっています。
また主人公自身が“自分とは何者なのか”という問いに向き合う旅でもあり、終盤に明かされる彼の正体と使命は多くのプレイヤーに強い印象を残しました。
ゲームシステム面では、前作『ドラゴンクエストⅤ』で一度廃止された職業システムが再び導入され、プレイヤーは転職を通じて自由にキャラクターを育成することができます。
職業ごとに異なる特技や呪文を習得でき、一定回数の戦闘をこなすことで熟練度が上がり、新たな職業への転職も可能になるなど、成長の自由度とやり込み要素が大きく向上しました。
この職業システムは後のシリーズ作品にも大きな影響を与えています。
また仲間キャラクターは個性豊かで、それぞれに独自の背景や目的を持っており、彼らの成長と物語への関与もプレイヤーの感情を深く揺さぶります。
バトルは従来通りのターン制コマンドバトルでありながらも、戦術の幅が広がったことで、戦闘の奥深さと楽しさが強化されています。
さらにモンスターを仲間にする要素も一部残されており、特定のスライム系モンスターなどを仲間にできるのも本作の魅力のひとつです。
音楽はすぎやまこういちによるもので、夢と現実をテーマにした幻想的で荘厳な旋律が印象的です。
フィールド曲やダンジョン曲、そしてクライマックスに向けて盛り上がる戦闘BGMなど、シリーズ屈指の名曲も多く生まれました。
発売当時はスーパーファミコン後期の代表的RPGとして注目され、国内での販売本数は約320万本を記録しました。
その後2010年にニンテンドーDSでフルリメイクが行われ、グラフィックの刷新やインターフェースの改善、仲間会話システムの導入などが追加され、より遊びやすい形で現代に蘇りました。
『ドラゴンクエストⅥ 幻の大地』は、シリーズの世界観をより深め、複層的な物語と自由な育成システムを融合させた意欲作であり、RPGファンにとって語り継がれる名作のひとつとなっています。
7位:ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち(FC)・・・304万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち |
| ゲームハード | ファミリーコンピュータ |
| 発売日 | 1990年2月11日 |
| 国内販売数 | 304万本 |
日本国内で7番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』です。
国内販売数は304万本となっています。
『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』は1990年2月11日にファミリーコンピュータ向けに発売された、シリーズ第4作目のナンバリングタイトルです。
本作は、従来の一本道型の冒険とは一線を画し、「章立て構成」という斬新な形式を採用しており、プレイヤーは複数のキャラクターたちの視点を追いながら、壮大な物語を紡いでいくことになります。
その革新的な演出と緻密なストーリーテリングは、当時のゲームファンに衝撃を与え、ドラゴンクエストシリーズにおける物語表現の可能性を大きく広げました。
物語は「第1章」から「第4章」まで、導かれし仲間たちそれぞれの視点で進行し、商人ライアン、姉妹マーニャとミネア、踊り子マーニャ、占い師ミネア、そしてトルネコ、勇敢な戦士たちの過去や動機が描かれます。
プレイヤーはそれぞれの物語を順に体験した後、「第5章」で主人公の視点に立ち、これまでの登場人物たちと合流し、世界を脅かす大いなる敵・地獄の帝王エスターク、そしてその背後に潜むデスピサロとの最終決戦へと挑んでいきます。
特に注目すべきは敵であるデスピサロの描写であり、単なる悪の存在ではなく、悲劇を背負った人物として描かれることで敵にも感情移入が生まれるという、当時としては非常に先進的な演出が施されています。
ラストに至るまでの展開にはプレイヤーに深い余韻を残すドラマ性が込められており、善悪の境界や人間の感情に迫るストーリーとしても評価されています。
ゲームシステム面では仲間キャラクターが増えていくことで戦略性が広がり、さらに「AI戦闘(作戦コマンド)」がシリーズで初めて導入されたことも大きな特徴です。
このシステムにより仲間たちはプレイヤーの指示なしに自動で戦ってくれるようになり、ゲームのテンポが向上するとともに、戦略の幅も広がりました。
音楽はすぎやまこういちが担当しており、各章ごとに異なるテーマ曲や、感動的なフィールドBGM、緊迫感あふれる戦闘曲など、物語と一体となった楽曲群が高く評価されています。
特に「間奏曲」や「導かれし者たち」のメインテーマは、今なおシリーズを象徴する楽曲としてファンに親しまれています。
発売当時の国内販売本数は約300万本に達し、ファミコン末期にもかかわらず圧倒的な人気を博しました。
その後プレイステーション、ニンテンドーDS、スマートフォンなどにも移植・リメイクされ、時代を超えて新たなファンにも受け入れられています。
『ドラゴンクエストⅣ 導かれし者たち』は、シリーズに物語性の深化をもたらした転機となる作品であり、多視点構成という大胆な手法を用いた革新的な名作として、現在も語り継がれています。
8位:ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁(SFC)・・・280万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁 |
| ゲームハード | スーパーファミコン |
| 発売日 | 1992年9月27日 |
| 国内販売数 | 280万本 |
日本国内で8番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』です。
国内販売数は280万本となっています。
『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』は1992年9月27日にスーパーファミコン向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズの第5作目にあたるナンバリングタイトルです。
“天空シリーズ”三部作の第2作目に位置づけられ、本作では主人公の少年時代から父となる壮年期まで、三世代にわたる人生と壮大な運命が描かれます。
プレイヤーはただ魔王を倒す勇者としてではなく、家族を持ち、運命に翻弄されながらも成長していく一人の人間としての物語を体験することになります。
物語の始まりはまだ幼い主人公が父・パパスと共に旅をする場面から始まります。
やがて少年期には予想もできない別離と悲劇が訪れ、青年期には結婚という大きな選択、さらには自らの子どもたちとの出会いが待ち受けています。
そして最終的には、“伝説の勇者”の血筋を巡る秘密と、天空の血を引く者たちの運命が明かされていきます。
このように他のシリーズ作品とは異なり、プレイヤー自身が人生の時間の流れを体感することができる構成は、多くのファンの心を強く打ちました。
本作最大の特徴のひとつが「仲間モンスターシステム」の導入です。
敵として登場するモンスターたちを倒すことで仲間にできるという斬新な仕組みは、戦術の幅を大きく広げただけでなく、プレイヤーに独自の冒険パーティを構築する楽しみをもたらしました。
キラーパンサー、ホイミスライム、スライムナイトなど、多くのモンスターたちが仲間として活躍し、愛着の湧く存在となります。
戦闘システムは従来のターン制コマンドバトルを踏襲しながらも、成長した家族やモンスターたちとともに戦うという点で、物語とプレイが強く結びついています。
またスーパーファミコンならではの表現力により、グラフィックやアニメーションも前作から大きく進化し、より深くドラマチックな演出が可能となりました。
そして本作を語るうえで欠かせないのが、物語中盤の「結婚イベント」です。ビアンカ、フローラ(後のリメイクではデボラも追加)という2人(もしくは3人)のヒロインの中から、誰と結ばれるかをプレイヤーが選択するシステムは、ストーリーに大きな影響を与えるのみならず、後のゲームにおける“選択と分岐”の表現にも大きな影響を与えました。
音楽はすぎやまこういちによるもので、テーマ性の強い旋律がプレイヤーの感情を揺さぶります。
特に「愛の旋律」や「哀しみの旋律」など、親子や家族の絆を象徴する名曲が多数収録されており、プレイ後も深い余韻を残します。
国内での販売本数は約280万本を記録し、後にプレイステーション2、ニンテンドーDS、スマートフォンなどでリメイクが重ねられたことで、より多くの世代に愛され続ける作品となりました。
『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』は、RPGに“人生”と“家族”という新たな視点を持ち込んだ先駆的な作品であり、今なおシリーズの中でも特に感動的な名作として、多くのプレイヤーに語り継がれています。
9位:ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々(FC)・・・240万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々 |
| ゲームハード | ファミリーコンピュータ |
| 発売日 | 1987年1月26日 |
| 国内販売数 | 240万本 |
日本国内で9番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』です。
国内販売数は240万本となっています。
『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』は1987年1月26日にファミリーコンピュータ向けに発売された、ドラゴンクエストシリーズ第2作目のナンバリングタイトルです。
前作『ドラゴンクエスト』の世界観と物語を受け継ぐ正式な続編であり「ロト三部作」の中編にあたる本作では、時代が100年後へと移り、勇者ロトの血を引く3人の子孫たちが新たな冒険へと旅立ちます。
本作はシリーズ初の「パーティ制」を導入した作品として歴史的な意義を持っています。
プレイヤーは最初、主人公である「ローレシアの王子」ひとりで冒険を始めますが、物語が進むにつれて「サマルトリアの王子」「ムーンブルクの王女」が仲間に加わり、3人で力を合わせて邪悪なる存在「ハーゴン」、そしてその背後に潜む真のラスボス「シドー」との激闘に挑むことになります。
個性の異なる仲間たちによる戦略的なバトルが可能となり、シリーズの基盤となるゲームシステムの多くがこの作品で確立されました。
舞台は前作よりも遥かに広大な世界で構成されており、複数の大陸や海、島々を船で巡ることで探索が進行します。
この「船による自由な移動」が導入されたことにより、プレイヤーの冒険は一気にスケールアップし、当時としては圧倒的な開放感と自由度を体感することができました。
また各地にはユニークな文化や伝承が存在し、世界を旅する楽しさが物語性と密接に結びついています。
戦闘はコマンド選択式で、敵の出現数が一体から複数体に増えたことでより高度な戦術とパーティの役割分担が求められるようになりました。
特に攻撃・回復・補助魔法を駆使した戦い方が重要であり、シリーズにおける“バトルの深み”が大きく進化した作品でもあります。
難易度は比較的高めで、特に後半のダンジョンやラストバトルは歯ごたえのある設計となっており、多くのプレイヤーが挑戦と試行錯誤を重ねながらクリアを目指しました。
音楽はすぎやまこういちによる荘厳かつドラマティックな旋律が全体を彩り、「遥かなる旅路」や「果てしなき世界」など、冒険のロマンを感じさせる名曲が多数生まれました。
これらの楽曲は後のシリーズ作品やコンサートでも繰り返し演奏されるなど、ドラゴンクエストの音楽的伝統を築いた礎とも言える存在です。
発売当時は前作の成功を受けて大きな注目を集め、国内での販売本数は240万本を超える大ヒットを記録しました。
その後も、スーパーファミコンやゲームボーイ、スマートフォンなどでリメイクや移植が行われ、今なお多くのファンに愛され続けています。
『ドラゴンクエストⅡ 悪霊の神々』は、シリーズの進化を象徴する重要な作品であり、複数の仲間、広大な世界、壮大な敵との戦いというRPGの原型を確立した金字塔として、ゲーム史に深く刻まれています。
10位:ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁(PS2)・・・161万本
| タイトル | ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁 |
| ゲームハード | PlayStation2 |
| 発売日 | 2004年3月25日 |
| 国内販売数 | 161万本 |
日本国内で10番目に売れたドラクエタイトルは『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』です。
国内販売数は161万本となっています。
『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』のプレイステーション2版は2004年3月25日にスクウェア・エニックスから発売された、シリーズ初のフル3Dリメイク作品です。
1992年にスーパーファミコンで登場した原作の名作をもとに、物語・キャラクター・システムを忠実に再現しつつ、グラフィックや演出を大幅に強化した本作は、感動的なストーリー体験を現代のプレイヤーにもたらす決定版として高く評価されました。
物語は、少年期・青年期・父親となる壮年期という三世代にわたって展開され、主人公の人生そのものを体験するような構成が特徴です。
父・パパスとの旅立ち、突如訪れる悲劇、奴隷としての過酷な日々、そして運命的な結婚と子どもたちとの再会――。
勇者の血を巡る物語でありながら、“家族”と“絆”を主軸に据えたシナリオは、シリーズの中でも特に深い感動を呼び、多くのファンの心に強く刻まれています。
プレイステーション2版では原作と同様に、結婚相手としてビアンカとフローラの2人の花嫁候補が登場します。
どちらを選ぶかによって、家族構成や一部のイベント内容が変化するため、プレイヤーの選択が物語の味わいに直結します。
この「人生を選ぶ」感覚はゲームに深い没入感を与え、単なる冒険譚にとどまらない人間ドラマを描き出しています。
戦闘はコマンド制を踏襲しつつも、グラフィックの進化によりキャラクターやモンスターが立体的に描かれ、より迫力あるバトルを実現しています。
仲間モンスターシステムも健在で、倒したモンスターが仲間になることで、自分だけの多様なパーティを編成する楽しさが広がります。
また戦闘参加人数が原作の3人から4人に拡張され、戦略性もより高まりました。
音楽はすぎやまこういちによる楽曲をフルアレンジし、シーンごとの感情表現を豊かに演出しています。
3Dグラフィックとの相乗効果により、名場面の数々がより一層心に残るものとなりました。
特に親子の再会やクライマックスの演出は、旧作以上にドラマティックなものへと昇華されています。
発売当時PS2の性能を活かしたリメイクとして注目され、原作ファンだけでなく新たなプレイヤー層にも支持されました。
『ドラゴンクエストⅤ 天空の花嫁』プレイステーション2版は、感動的なストーリー、自由度の高い育成、そして家族との絆を描いた深いテーマ性が融合した、シリーズ屈指の名作として今なお色褪せない魅力を放っています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、日本国内で最も売れたドラゴンクエストタイトルトップ10をご紹介しました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
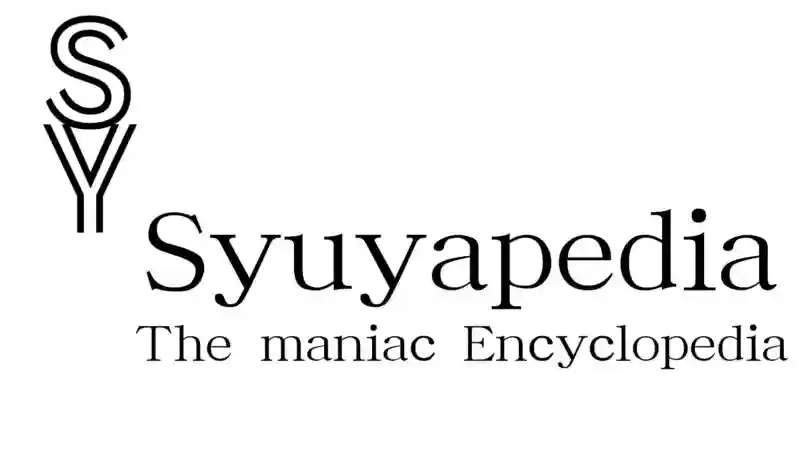
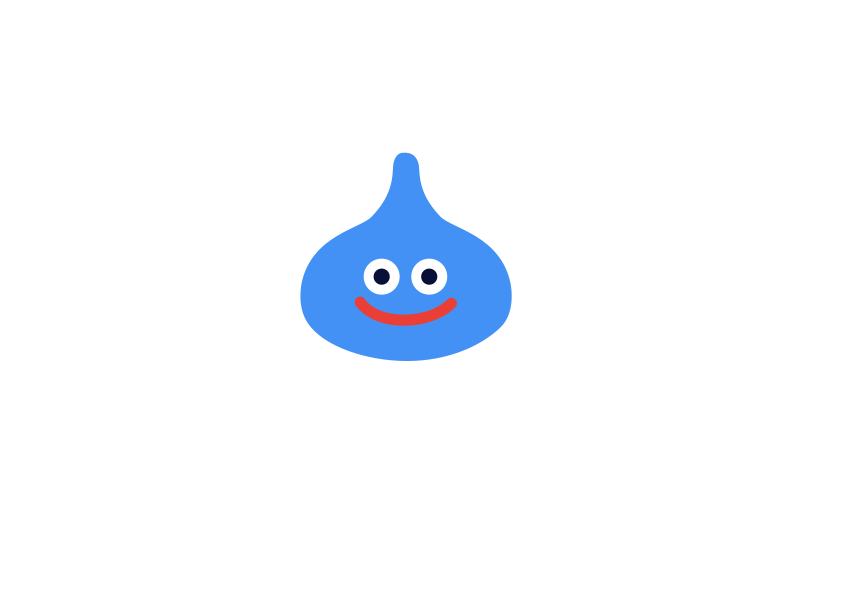
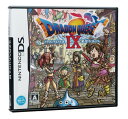
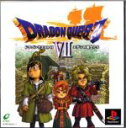
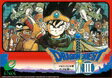
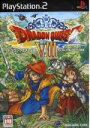
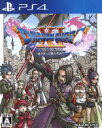
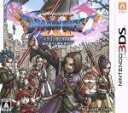
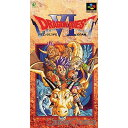
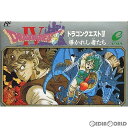
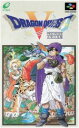
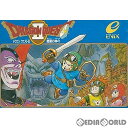
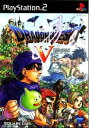


コメント