スタジオジブリ作品の内、国内映画興行収入ランキングトップ10の作品をご紹介しています。
みなさんこんにちは、syuyaです。
この記事ではスタジオジブリの映画作品の、国内興行収入ランキングトップ10をご紹介しています。
スタジオジブリは昭和60年に設立され、日本アニメーション史において独自の地位を築いてきました。
設立当初は宮崎駿と高畑勲を中心に長編アニメーション映画の制作を目的として活動を始め、『未来少年コナン』や『ルパン三世 カリオストロの城』、『風の谷のナウシカ』といった最初期の大きな成功を収めた作品群によってその名は国内外に広まりました。
その後、1985年にスタジオジブリを設立、1986年にはスタジオジブリとしての初めての長編映像作品『天空の城ラピュタ』が放映されます。
以降、スタジオは安定的に長編映画を発表し、商業的な成功と芸術的評価を両立させる稀有な存在となりました。
ジブリ作品の特徴は、まず緻密で美しい手描きアニメーションにあります。
自然描写の細やかさや、風や光といった目に見えにくいものまで丁寧に表現することで、画面全体に豊かな生命感が宿っています。
また、キャラクター造形においても善悪が単純に分かれることはなく、それぞれの立場や価値観を持った多面的な人物像が描かれるのが大きな魅力です。
さらに、少女を中心とした成長物語や、人間と自然との関わりを軸にしたテーマが繰り返し取り上げられ、寓話的でありながらも現実に通じる普遍性を持っています。
音楽もジブリ作品を特徴づける要素であり、久石譲をはじめとする作曲家たちが手掛けた楽曲は、映像と一体となって深い余韻を残します。
その旋律は作品の雰囲気を支えるだけでなく、独立した音楽としても広く親しまれています。
こうした総合的な表現力により、ジブリの作品群は世代や国境を超えて人々の記憶に残り続けており、日本を代表する文化的存在として世界的な評価を得ています。
この記事では、そんなスタジオジブリの国内興行収入ランキングトップ10をご紹介しています。
1位:千と千尋の神隠し・・・316.8億円
| タイトル | 千と千尋の神隠し |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 2001年 |
| 国内興行収入 | 316.8億円 |
ストーリー
10歳の少女・千尋は、両親と共に引っ越し先へ向かう途中、不思議なトンネルを抜けて異世界に迷い込みます。そこは神々や妖怪が集い、油屋という大浴場を中心に栄える独特の世界でした。両親は食べ物を勝手に口にしたことで豚に姿を変えられ、千尋は孤独と恐怖に包まれながらも、元の世界へ帰るために油屋で働く決意を固めます。そこで出会った少年ハクや釜爺、リンといった仲間たちとの交流を通じて、彼女は少しずつ勇気と自立心を育んでいきます。
油屋を支配する魔女・湯婆婆との契約により「千」と名を奪われながらも、千尋は数々の困難を乗り越えていきます。暴れる神をもてなし、自らの正体を失ったカオナシと向き合い、そしてハクの隠された過去と悲惨な現状を知り、ハクを救うために奔走する事で、千尋は人間的に大きく成長していきます。
『千と千尋の神隠し』はスタジオジブリの代表作であると同時に、日本映画史に残る金字塔的作品です。
公開当時圧倒的な興行収入を記録し、長らく国内映画の頂点に立ち続けただけでなく、アニメーションという枠を超えて一大社会現象を巻き起こしました。
本作の魅力は、まずその幻想的かつ緻密な世界観にあります。
八百万の神々が暮らす異世界は、日本の神話や伝承を下敷きにしながらも、独自の創造力によって生み出され、現実と非現実が融合した不思議な空間として描かれています。
主人公である千尋は最初は頼りなく臆病な少女として描かれますが、両親を救い出すために困難を乗り越える過程で、逞しさや優しさを身につけていきます。
その成長譚は、観る者に「自分もまた逆境を乗り越えられるのではないか」という勇気を与え、単なるファンタジーを超えた普遍的な共感を呼び起こします。
また欲望に支配された大人たちや、名前を奪う契約といったモチーフには現代社会への批評性も潜んでおり、子どもにとっては冒険物語、大人にとっては寓話的な人間ドラマとして二重に楽しめる構造になっています。
さらに久石譲の音楽が映像と一体化し静謐さと高揚感を絶妙に行き来する旋律は、物語の余韻を深めています。
美術面においても、光や影、水や風といった自然の表現に徹底してこだわることで、アニメーションでありながら実際に存在するかのようなリアリティを持たせています。
こうした要素が総合的に組み合わさり、『千と千尋の神隠し』は国際的にも高い評価を受け、アカデミー賞長編アニメーション賞をはじめとする数々の賞を獲得しました。
また、本作は日本映画史上においても記録的となる興行収入を達成し、2020年に『劇場版「鬼滅の刃」無限列車編』に記録を塗り替えられるまで、約20年間に渡り日本の映画興行収入ナンバー1の記録を保持していました。
本作はスタジオジブリの芸術性と大衆性を両立させた頂点であり、今なお世界中の観客に深い感動を与え続けています。
2位:もののけ姫・・・201.8億円
| タイトル | もののけ姫 |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 1997年 |
| 国内興行収入 | 201.8億円 |
ストーリー
北の村に暮らす青年アシタカは、村を襲ったタタリ神を討ち取った際に呪いを受け、死を避けるために西の地へ旅立ちます。旅の途中で謎の男ジコ坊との出会いを経つつ、旅の果てにたどり着いたのは、人間の文明と森の神々が激しく対立する地でした。そこでアシタカは森に生きる少女サンと出会い、その自然と調和して生きる姿に心惹かれます。そしてその地には、アシタカの村を襲ったタタリ神を作った元凶となった、自然を破壊し切り拓く事で栄えたたたら場の街があり、アシタカはその街を統べるエボシ御前と謁見します。アシタカは自然を破壊するエボシ御前に憎しみの感情を抱く一方で、たたら場の人間達の温かさや一生懸命に生きる様子に心を動かされます。そんなある夜に、たたら場をサンが襲撃します。結果返り討ちにあったサンを庇い、自らも重傷を負いつつも、アシタカは気を失ったサンを抱え森へと姿を消します。サンを村から連れ出したアシタカは、サンが目を覚ますのと入れかわりに、意識を失います。その後、サンの看病の成果もあって目を覚ましたアシタカは、そこでサンの育ての親であり、山犬たちの長であったモロの君と出会い、山犬に育てられたサンの生い立ちを知ります。アシタカとサンは、自然を切り拓く人間たちと森を守ろうとする精霊や獣たちの争いの狭間で、自らの生き方を模索していきます。
『もののけ姫』は、スタジオジブリが放った壮大な叙事詩であり、宮崎駿のキャリアの中でも転換点となった作品です。
中世日本を想起させる世界を舞台に、人間の欲望と自然の力が激突する物語は、従来の「勧善懲悪」という枠組みを超え、善悪の曖昧さや価値観の相違を真正面から描きました。
登場人物たちはそれぞれの信念を持ち、森を切り拓くエボシ御前の行動には人間社会の発展という理があり、一方でサンや森の神々には自然を守ろうとする必死の想いが宿っています。
その両者の対立は単純な勝敗ではなく、人間と自然の共生という普遍的な問いを投げかけています。
映像表現においては緻密な背景美術と迫力あるアクションシーンが融合し、森の神々や獣たちが持つ荘厳さと畏怖を見事に描き出しています。
またタタリ神やシシ神といった存在は、日本古来の自然観やアニミズムを基盤にしながらも、独創的なデザインと演出によって観客に強烈な印象を与えました。
音楽面では久石譲による重厚で荘厳な楽曲が物語に深みを加え、映像とともに神秘的な世界観を作り上げています。
公開当時、『もののけ姫』は日本映画史上空前の大ヒットを記録し、その年の文化的象徴となりました。
また、海外でも高い評価を受け、スタジオジブリ作品が国際的に注目されるきっかけのひとつとなりました。
この作品は単なるアニメーション映画を超え、人間と自然、文明と命の在り方を問い直す重厚なテーマを持つ作品として、今もなお多くの観客に強い余韻を残しています。
3位:ハウルの動く城・・・196億円
| タイトル | ハウルの動く城 |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 2004年 |
| 国内興行収入 | 196億円 |
ストーリー
主人公のソフィーは街の帽子屋で働く、ごく普通の若い女性でした。ある日、街で美しい魔法使いハウルと出会ったことをきっかけに、荒地の魔女から呪いをかけられ、九十歳の老婆の姿に変えられてしまいます。家を飛び出したソフィーは、流浪の末に不思議な「動く城」に辿り着き、そこに住むハウルや炎の悪魔カルシファー、弟子のマルクルと奇妙な共同生活を始めます。
ソフィーは自分の呪いを解く手掛かりを探しながら、心を閉ざし人との関わりを避けてきたハウルに触れ、その人間らしい弱さや優しさを知っていきます。一方で国は戦争に突入し、魔法使いたちも軍に召集されるなど、争いの影が城の生活にも及び始めます。ハウルは戦争を嫌悪しながらも、強大な魔力を用いてソフィーたちを守ろうとしますが、その力の代償に心が蝕まれ、次第に自らを制御できなくなっていきます。
ソフィーは自分に課せられた呪いを恐れず、むしろそれを受け入れながら、ハウルの本当の姿や心の傷に寄り添うことで、彼を支えようと決意します。やがてソフィーの真摯な想いと行動は、ハウルだけでなく、カルシファーや荒地の魔女をも変えていき、破滅へと傾いていた戦争の流れに一石を投じていきます。
『ハウルの動く城』は、イギリスの作家ダイアナ・ウィン・ジョーンズによる小説を原作としながら、宮崎駿独自の解釈を加えて映画化されたスタジオジブリ作品です。
空を歩く巨大な城、自在に形を変える扉など、幻想的でダイナミックな映像表現は公開当時大きな話題を呼び、観客を圧倒しました。
特に城の内部に描かれる雑然としながらも温かみのある空間は、ジブリならではの生活感に満ちており、現実感とファンタジーが見事に融合しています。
物語は少女ソフィーの成長譚であると同時に、臆病さを抱えながらも人を愛し守ろうとするハウルの人間的な弱さと強さを描き出しています。
戦争という重いテーマが背景に据えられており、荒廃する世界の中で愛と希望を見いだす物語として、多層的な読み解きが可能になっています。
また、久石譲によるワルツ調の音楽は、幻想的でありながらどこか郷愁を誘う響きで作品全体を包み込み、観客に深い余韻を残しました。
本作は国内で大ヒットを記録したのみならず、国際的にも高い評価を得ており、アカデミー賞長編アニメーション賞にノミネートされるなど、ジブリ作品の世界的な認知をさらに広める契機となりました。
『ハウルの動く城』は、宮崎駿が持つ映像美、ファンタジー性、そして反戦的メッセージが融合した作品であり、観る者に愛と想像力の力強さを改めて感じさせる一本として位置づけられています。
4位:崖の上のポニョ・・・155億円
| タイトル | 崖の上のポニョ |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 2008年 |
| 国内興行収入 | 155億円 |
ストーリー
海辺の町に暮らす五歳の少年・宗介は、ある日、海岸で金魚のような姿をした不思議な少女を助け、「ポニョ」と名づけます。実はポニョは、海の魔法使いフジモトと海の女神グランマンマーレの娘で、本来は人間ではなく海に生きる存在でした。しかし、宗介との出会いを通じて人間の世界に強く惹かれるようになり、自らの魔法の力を使って人間の姿へと変わろうとします。
ポニョの行動は、やがて自然界の均衡を崩してしまい、満ち潮や大波などの異変を引き起こします。宗介の町は大洪水に見舞われ、世界は海に呑み込まれてしまう危機に瀕しますが、それでも宗介は必死にポニョを守り抜こうとします。ふたりは嵐に揺れる世界の中で小さな船旅に出て、宗介の母・リサや町の人々を探しながら、互いの絆を深めていきます。
やがてポニョの母グランマンマーレが現れ、ポニョが本当に人間として生きるか、それとも海に戻るかを決めなければならない時が訪れます。その試練の中で、宗介が無条件の愛と受け入れる心を示すことによって、ポニョは人間の少女として生きる道を選び、世界も再び安定を取り戻します。
『崖の上のポニョ』は、宮崎駿が「子どもたちのための映画を作りたい」という思いを込めて制作したファンタジー作品です。
その映像は全編手描きにこだわり、柔らかく温かみのある線と鮮やかな色彩によって、童話のような世界を生み出しました。
特に海の動きや波のうねりは、キャラクターのように生命力を持って描かれ、画面全体が常に躍動感に満ちています。
物語は人間と自然、そして親子や子ども同士の絆を軸に描かれています。
ポニョが人間になることを望む姿は、自由への憧れや成長の象徴であり、宗介との絆は純粋な愛と信頼の力を示しています。
一方でフジモトやポニョの母グランマンマーレといった存在は、自然界の大きな力や畏怖を体現しており、物語に神話的な深みを与えています。
音楽面では久石譲によるスコアが優雅さと躍動感を兼ね備え、物語の幻想性をさらに高めました。
特に主題歌「崖の上のポニョ」はシンプルで親しみやすい旋律が広く支持され、子どもから大人まで幅広い層に親しまれる一因となりました。
公開当時、本作は圧倒的な動員を記録し、日本国内のみならず海外でも注目を集めました。
その明快で力強いビジュアルと、普遍的なテーマによって、『崖の上のポニョ』はスタジオジブリの中でも特に子どもたちに強く愛される作品となっています。
5位:風立ちぬ・・・120億円
| タイトル | 風立ちぬ |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 2013年 |
| 国内興行収入 | 120億円 |
ストーリー
幼い頃から飛行機に強い憧れを抱いていた堀越二郎は、近眼のため自ら操縦士になる夢を断念しますが、設計技師として空を飛ぶ夢を叶えることを決意します。夢の中で憧れの存在であるイタリアの飛行機設計者カプローニと出会い、彼から「技師として生きる道」を示され、二郎は大空を翔ける機体を生み出すことを人生の目標とします。
やがて青年となった二郎は、大学で工学を学び、三菱内燃機に入社。日本の航空技術が欧米に大きく遅れを取る現実に直面しながらも、試行錯誤を重ね、次第に頭角を現していきます。その過程で訪れた軽井沢で、美しい少女・菜穂子と再会します。幼少期の関東大震災で偶然出会った彼女との縁が再び結ばれ、二人は恋に落ちるのです。
しかし、菜穂子は重い結核を患っており、幸せな日々は長く続かないことを二郎は知ります。それでも二人は強い思いで結ばれ、互いに寄り添いながら結婚生活を送ります。やがて病状が悪化した菜穂子は、自ら療養所へ戻る決意をし、二郎の夢を支えるために静かに彼の前から姿を消します。
時代は戦争へと突き進み、二郎の設計した零式艦上戦闘機は、日本の空を覆う主力機として生み出されます。しかしその背後には、彼が心から望んだ「美しい飛行機の夢」と、戦争という現実の矛盾が重くのしかかります。
『風立ちぬ』は実在の航空技術者・堀越二郎の生涯をモデルにしつつ、堀辰雄の小説『風立ちぬ』の要素を織り交ぜた、フィクションと史実を融合させた作品です。
スタジオジブリ作品の中でも特に現実的な世界観を基盤とし、ファンタジー色をほとんど排している点が特徴的です。
飛行機という工業製品を「夢」として美しく描く一方で、それがやがて戦争の道具となるという皮肉を背負っており、理想と現実の相克が物語の大きなテーマとなっています。
本作における宮崎駿のアニメーションは、実在の風景や時代背景を緻密に描写することで、日本の近代史を生きた人々の息遣いを生々しく感じさせます。
飛行機の設計図面や試作機の描写は細部までこだわり抜かれ、空を飛ぶシーンは夢想的な美しさをたたえています。
一方で二郎と菜穂子の関係性は繊細かつ切実に描かれ、愛する人を支えながら夢を追うことの喜びと悲哀が胸を打ちます。
音楽は久石譲ではなく、ピアニスト・作曲家の久石譲以外のアーティストが手掛けるのではなく、実際には久石譲が担当しており、軽やかでありながら深い情感を持った旋律が作品全体を支えています。
特にイタリアの作曲家ナポリ民謡「ひこうき雲」を主題歌に据えることで、物語に時代を超えた普遍的な響きを与えました。
『風立ちぬ』は公開当時、宮崎駿の引退作として位置づけられたこともあり、大きな注目を集めました。
その後に復帰が発表されましたが、本作は宮崎駿のキャリアにおいて「夢を追うことの代償」を真正面から描いた重厚な作品として、異彩を放っています。
ファンタジーを得意とするジブリ作品の中にあって、現実の歴史を背景にした本作は、観客に強い余韻と深い思索を残しました。
6位:君たちはどう生きるか・・・94億円
| タイトル | 君たちはどう生きるか |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 2023年 |
| 国内興行収入 | 94億円 |
ストーリー
物語は太平洋戦争期前後の日本を背景に、母親を失い田舎へ疎開した少年・眞人(まひと)が主人公です。眞人は新しい家の近くにある廃塔で「灰色のサギ(=あの鳥の姿をした謎の存在)」と出会い、その導きによって現実と幻想が交錯する「下の世界」へ足を踏み入れます。そこで眞人は自分の内にある喪失感や罪悪感、あるいは大人たちの言動が生む不条理と向き合うことを強いられます。作品は単なる冒険譚にとどまらず、喪失からの再生や成長、そして「どう生きるか」という根源的な問いに向き合う少年の精神的な旅路を描いています。タイトルは吉野源三郎の同名の書籍に由来しますが、原作の直訳ではなく、宮﨑の独自の物語世界として再構成されています。
『君たちはどう生きるか』は、宮﨑駿が長年温めてきた主題──喪失と成長、夢と現実、個と社会の関係──を、より熟成した語り口で提示した作品です。
映像的には伝統的な手描きアニメーションの技巧が随所に発揮され、現実の風景描写と幻想的な「下の世界」との対比を通じて、観客に視覚的にも感覚的にも強い印象を残します。
物語構造は多層的で、子ども向けの冒険譚としての顔と、大人が噛めば噛むほど味の出る寓意的・哲学的な面を同居させています。
これは主人公の内面の変化を丁寧に描くことで、「生きる意味」や「他者との関わり」を観る者自身に考えさせる作りになっている点が特徴です。
公開時にはスタジオ側の意図的な露出制限(宣伝を極力控える手法)が話題になり、作品そのものが観客との「遭遇」を重視するような配給方針が取られました。
批評面ではそのテーマ性と映像表現が高く評価され、国際的な映画賞でも多数の栄誉を受けています。
とりわけ第96回アカデミー賞で長編アニメーション賞を受賞するなど、日本のアニメーション史における重要作の一つとして位置づけられました。
総じて本作は、宮﨑駿という作家の思想と技術の集大成の一端を示すと同時に、観る者に「自分はどう生きるのか」を静かに問いかけ続ける作品です。
年齢や文化を超えて様々な解釈を許す余地を残す作りになっているため、鑑賞層ごとに異なる受け取り方が生まれる──それ自体が本作の大きな魅力でもあります。
7位:借りぐらしのアリエッティ・・・92.6億円
| タイトル | 借りぐらしのアリエッティ |
| 監督 | 米林宏昌 |
| 公開年 | 2010年 |
| 国内興行収入 | 92.6億円 |
ストーリー
人間の家の床下に暮らす小人たちは、人に気づかれないように生活し、生活に必要なものを少しだけ「借りて」生きています。14歳の少女アリエッティもまた、両親と共にひっそりと暮らしていましたが、病気療養のためにやってきた人間の少年・翔に姿を見られてしまいます。小人たちにとって人間は脅威であり、接触は避けるべきものとされていましたが、翔の優しい心に触れるうちに、アリエッティは恐怖と興味、そして心の交流の間で揺れ動きます。二人の間には確かな信頼が芽生えるものの、異なる存在であるがゆえに一緒には生きられないという現実が立ちはだかります。別れを前提とした出会いの切なさを通じて、アリエッティは小さな命の誇りを胸に未来へ踏み出していきます。
『借りぐらしのアリエッティ』はイギリスの児童文学「床下の小人たち」を原案に、スタジオジブリが独自の解釈を加えて映像化した作品です。
脚本は宮崎駿が担当し、監督には当時若手の米林宏昌が抜擢されました。本作の大きな特徴は、アリエッティたち小人の視点から描かれる世界の圧倒的なスケール感と臨場感にあります。
針や糸、葉や水滴といった日常の些細なものが巨大に映し出されることで、観客は普段の生活の中に潜むもう一つの宇宙に触れるような感覚を味わえます。
また、自然や家の中の細部を丁寧に描き出すことで、小人たちの暮らしにリアリティを与えています。
音楽面では、フランスの歌手セシル・コルベルによる透明感のあるハープと歌声が印象的で、作品全体に幻想的で異国的な空気を漂わせています。
人間と小人という異なる存在が互いを理解しようとする姿を通じて、共生や尊重の大切さを静かに訴えかける本作は、スタジオジブリの新しい可能性を示すと同時に、観客に余韻深い問いを残す作品となりました。
8位:ゲド戦記・・・76.5億円
| タイトル | ゲド戦記 |
| 監督 | 宮崎吾朗 |
| 公開年 | 2006年 |
| 国内興行収入 | 76.5億円 |
ストーリー
広大な海と島々から成る「アースシー」の世界では、かつて調和と秩序をもたらしていた力の均衡が崩れつつありました。自然が乱れ、動物たちは不安に怯え、人々もまた生きる力を失いかけています。その中で、王国の若き王子アレンは、心の闇に呑まれて父王を手にかけてしまい、罪を背負って国を捨て、荒野をさまよいます。絶望と恐怖に取り憑かれた彼は、旅の途中で偉大な大賢人ゲドと出会い、彼の導きのもとで共に旅をすることになります。
二人は、奴隷商人に囚われた人々を助け、かつてのゲドの友人である女性テナーや、彼女と暮らす少女テルーと出会います。テルーは心に深い傷を抱えており、他者との関わりを拒むようにして生きていましたが、アレンと触れ合う中で次第に心を開いていきます。その一方で、世界の均衡を崩す元凶は、不老不死を求める魔法使いクモの存在にあることが明らかとなっていきます。クモは死を恐れるあまり禁忌の術を用い、命の理を乱していました。
アレンはクモの誘惑に引き込まれ、自らの弱さに翻弄されながらも、最終的にはその闇と正面から向き合います。テルーの存在が彼を支え、彼女が大地と生命を象徴する存在であることが示されることで、アレンはようやく自分の過ちを受け入れ、未来へ進む勇気を得ます。
『ゲド戦記』は、アーシュラ・K・ル=グウィンのファンタジー小説「アースシー」シリーズを原案とし、スタジオジブリが独自の解釈で映像化した作品です。
監督を務めたのは宮崎駿の長男・宮崎吾朗であり、これが彼の初監督作品となりました。ジブリ作品における世代交代を象徴する一本であり、公開当時は大きな話題と共に賛否両論を巻き起こしました。
映像表現では、広大な海や大地を背景に、生命の営みと世界の均衡を巡る壮大な物語が描かれています。
自然や街並みの細部まで緻密に描かれた美術、そして登場人物たちの静かで重厚な心理描写は、従来のジブリ作品とは異なる独特の雰囲気を生み出しています。
また寺島しのぶや菅原文太、田中裕子といった豪華声優陣による演技が、登場人物たちに深みを与えました。
さらに、挿入歌として登場する「テルーの唄」は、作品全体の象徴ともいえるほど強い印象を残し、公開当時に大きな反響を呼びました。
テーマの中心にあるのは「生と死」「光と影」「恐れと勇気」という普遍的な問いです。
アレンの内面の葛藤や、テルーとの交流を通じた心の再生の物語は、観る者に人間の弱さと可能性を改めて問いかけます。
原作から大きく改変されたことで議論を呼びましたが、その独自性こそがジブリ作品の新しい挑戦であり、同時に宮崎吾朗監督の表現者としての第一歩を示した作品でもあります。
9位:猫の恩返し・・・64.8億円
| タイトル | 猫の恩返し |
| 監督 | 森田宏幸 |
| 公開年 | 2002年 |
| 国内興行収入 | 64.8億円 |
ストーリー
高校生のハルは、ある日トラックに轢かれそうになった猫を助けます。ところがその猫は言葉を話す王子であり、命を救った礼として猫の国へ招待されることになります。突然現れた猫たちの行列に翻弄されながら、ハルは望んでもいない贈り物を受け取り、ついには猫の王子と結婚させられそうになります。
困惑するハルは、謎の白猫ユキに導かれて「猫の事務所」を訪れ、そこにいるバロンやムタといった仲間に助けを求めます。猫の国へ連れて行かれたハルは、次第に自身も猫へと変わっていく危機に直面しますが、バロンの導きやユキの優しさ、そして自分自身の心の強さによって運命を切り開いていきます。やがて猫の国を脱出したハルは、元の世界に戻ると同時に、自らの中に眠っていた勇気と自立心に気づき、日常を前向きに生きようとする成長を遂げるのです。
『猫の恩返し』はスタジオジブリの長編アニメーションとして制作され、森田宏幸が初めて監督を務めた作品です。
原作は柊あおいの漫画「バロン 猫の男爵」で、『耳をすませば』に登場したキャラクター・バロンが物語の重要な役割を担うスピンオフ的な作品でもあります。
ファンタジックな世界観の中で、等身大の少女が非日常の冒険を通じて成長していくというテーマは、ジブリ作品の中でも親しみやすく、軽快で明るい物語運びが特徴的です。
映像面では鮮やかで柔らかい色彩と、猫たちのユーモラスで生き生きとした動きが作品全体を彩り、軽妙で夢のある世界を形作っています。
また、猫の国の独創的なデザインや、キャラクターたちの個性豊かな表情が、観客を自然と物語に引き込んでいきます。
音楽面でも、明るさの中に温かみを持つ旋律が、作品の軽快な雰囲気を際立たせています。
『猫の恩返し』は、他のジブリ作品に比べると比較的短い尺とシンプルな物語でありながら、主人公の成長や異世界での冒険、仲間との出会いといった王道の要素が凝縮されており、幅広い世代に親しまれています。
ユーモアと幻想性が調和した本作は、ジブリ作品の中でも特に気軽に楽しめる一方で、自分を信じて前に進む勇気を与えてくれる魅力を備えた作品です。
10位:紅の豚・・・54億円
| タイトル | 紅の豚 |
| 監督 | 宮崎駿 |
| 公開年 | 1992年 |
| 国内興行収入 | 54億円 |
ストーリー
舞台は第一次世界大戦後のイタリア・アドリア海。空賊が横行する時代に、豚の姿へと変えられた元エースパイロット、ポルコ・ロッソは賞金稼ぎとして空を駆けていました。彼は孤高の存在として空賊たちを退けつつも、過去の戦争体験や人間社会への失望を胸に秘め、人間として生きることを拒むように生きていました。
ある日、アメリカからやってきた自信家のパイロット、カーチスとの戦いに敗れ、愛機が大破してしまいます。修理を依頼したのは飛行艇工房の若き技師フィオ。彼女の情熱とひたむきさに触れる中で、ポルコは次第に心を揺さぶられていきます。一方、かつての友人であり今も密かに想いを寄せるジーナとの関係もまた、ポルコの心に大きな影を落としています。
そしてフィオを賭けたカーチスとの再戦が決まり、ポルコは再び闘志を燃やすのでした。
『紅の豚』は宮崎駿監督が「大人のためのアニメーション映画」を志して制作したスタジオジブリの異色作です。
子ども向けの冒険譚とは一線を画し、戦争後の空虚さや失望、愛や誇りといった普遍的なテーマを重厚に描き出しています。
特に主人公が豚の姿をしているという設定は、皮肉やユーモアを交えながら人間の弱さや矛盾を象徴的に示しており、寓話的な魅力を持ちます。
映像表現では、透き通るようなアドリア海の青や赤い飛行艇の鮮烈な色彩、そして空戦シーンの迫力が印象的で、飛行機やメカニックに対する宮崎駿のこだわりが存分に発揮されています。
また、久石譲による音楽は、哀愁とロマンに満ちた旋律で物語を彩り、大人の鑑賞に耐えうる深みを与えています。
本作は単なる冒険活劇にとどまらず、人間としての誇りを守り抜くこと、そして愛する者との静かな絆をどう生きるかを問いかける作品です。
軽妙なユーモアと深い人生観が交差する『紅の豚』は、スタジオジブリの中でも特に成熟した魅力を持ち、長く愛され続ける一本となっています。
まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事ではスタジオジブリ作品の内、国内興行収入ランキングトップ10の作品をご紹介しました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
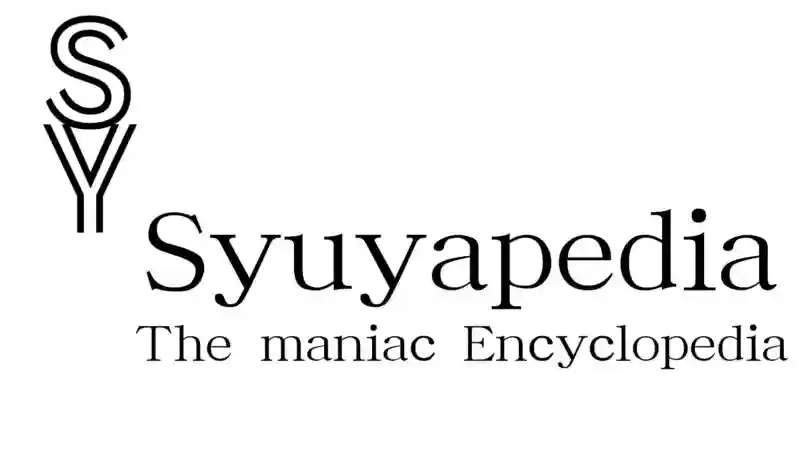



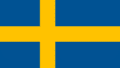
コメント