スクウェア(スクウェア・エニックス)より発売されている”ファイナルファンタジー”シリーズの、国内販売数ランキングトップ10がわかります。
ファイナルファンタジーシリーズは、スクウェア(現スクウェア・エニックス)によって開発・発売されている、日本を代表するロールプレイングゲーム(RPG)シリーズです。
第1作『ファイナルファンタジー』は1987年12月18日にファミリーコンピュータ向けに発売され、当初は会社の存続を賭けた最後の挑戦とされていましたが、その予想を超える大ヒットによって、以降長年にわたって続く人気シリーズの礎を築きました。
本シリーズの最大の特徴は、各ナンバリング作品ごとに物語、世界観、登場人物、ゲームシステムが大きく異なるという構成にあります。
中世ファンタジーから近未来、スチームパンク、さらには異世界や政治劇に至るまで、実に多彩な舞台設定とテーマを取り入れており、作品ごとにまったく異なる雰囲気やメッセージを持っています。それにより、常に新しい驚きと感動をプレイヤーに提供してきました。
ファイナルファンタジーシリーズは、家庭用ゲーム機だけでなく、携帯機やスマートフォン、PC、さらには映画やアニメ、小説といった多様なメディア展開も行っており、累計売上は全世界で1億8000万本を超えるとされます。
世界的な知名度を持つ日本発のゲームシリーズとして、ドラゴンクエストシリーズと並び、国産RPGの金字塔的存在です。
シリーズは現在も進化を続けており、最新作ではリアルタイムアクションやオープンワールドといった現代的要素も積極的に取り入れられています。
30年以上にわたり時代の最先端を走り続けてきたファイナルファンタジーは、常に「変わり続けること」を恐れず、挑戦と革新を重ねてきた作品群であり、その歴史と影響力は、世界のゲーム文化に多大な足跡を残しています。
この記事では、そんなファイナルファンタジーシリーズの国内販売数ランキングトップ10をご紹介しています。
- 1位:ファイナルファンタジーVII(PS1)・・・400万本
- 2位:ファイナルファンタジーVIII(PS1)・・・370万本
- 3位:ファイナルファンタジーIX(PS)・・・280万本
- 4位:ファイナルファンタジーX(PS2)・・・273万本
- 5位:ファイナルファンタジーV(SFC)・・・245万本
- 6位:ファイナルファンタジーXII(PS2)・・・223万本
- 7位:ファイナルファンタジーX-2(PS2)・・・211万本
- 8位:ファイナルファンタジーXIII(PS3)・・・187万本
- 9位:ファイナルファンタジーXV(PS4・Xbox One)・・・147万本
- 10位:ファイナルファンタジーIV(SFC)・・・144万本
- まとめ
1位:ファイナルファンタジーVII(PS1)・・・400万本
| タイトル | ファイナルファンタジーVII |
| ゲームハード | PlayStation |
| 発売日 | 1997年1月31日 |
| 国内販売数 | 400万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で最も売れた作品は『ファイナルファンタジーVII』です。
国内販売数は約400万本となっています。
ファイナルファンタジーVIIは1997年1月31日にソニーの家庭用ゲーム機プレイステーション向けに、スクウェア(現スクウェア・エニックス)から発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第7作目にあたり、それまでスーパーファミコンで展開されてきたシリーズが初めてCD-ROM媒体の次世代機に移行した作品であり、ゲーム業界における技術的、表現的な飛躍を象徴するタイトルとして知られています。
本作は近未来的な都市「ミッドガル」から物語が始まります。
主人公クラウド・ストライフは、かつて神羅カンパニーの精鋭戦闘員「ソルジャー」として活動していた元兵士で、現在は反神羅組織アバランチの依頼を受けて活動しています。
星の生命エネルギー「魔晄」を搾取し続ける神羅の腐敗に立ち向かう中で、クラウドは自身の過去と正体に向き合いながら、やがて世界を滅ぼそうとする宿敵セフィロスとの壮大な戦いへと身を投じていきます。
ファイナルファンタジーVIIは、当時としては最先端の3Dポリゴン技術とプリレンダリング背景を用いたグラフィックで、従来のRPGとは一線を画する映像表現を実現しました。
随所に挿入されるフルCGムービーは映画的な演出を可能にし、プレイヤーに強い没入感を与えました。
またバトルシステムは従来のATB(アクティブ・タイム・バトル)を踏襲しつつ、「マテリア」システムというカスタマイズ性の高い育成要素を導入し、戦略性と自由度を兼ね備えたプレイスタイルを確立しています。
登場キャラクターたちも非常に個性豊かで、ティファ、エアリス、バレット、ヴィンセント、ユフィなど、仲間たちの人間ドラマや背景にも多くのファンが魅了されました。
中でも物語の中盤に訪れる衝撃的な展開や、クラウドの記憶に関する謎の描写は、プレイヤーの心に強く残るものとなっています。
音楽面でも極めて高い評価を受けており、作曲家・植松伸夫による楽曲群は、壮大さと繊細さを兼ね備え、ストーリーの感情の機微を見事に表現しています。
「エアリスのテーマ」「更に闘う者たち」「片翼の天使」などの楽曲は、今なお多くのファンに愛され、コンサートやリメイク作品でも重要な位置を占めています。
ファイナルファンタジーVIIは全世界で1000万本以上の販売本数を記録し、単なるゲーム作品を超えて、リメイク・映像化・ノベライズ・スピンオフ作品など幅広いメディア展開を果たした、まさに一時代を築いたタイトルです。
RPGというジャンルを世界規模で普及させた代表作であり、その革新性と深い人間ドラマは、今なお多くの人々の記憶に残り続けています。
2位:ファイナルファンタジーVIII(PS1)・・・370万本
| タイトル | ファイナルファンタジーVIII |
| ゲームハード | PlayStation |
| 発売日 | 1999年2月11日 |
| 国内販売数 | 370万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で2番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーVIII』です。
国内販売数は約370万本となっています。
ファイナルファンタジーVIIIは1999年2月11日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)からプレイステーション向けに発売されたロールプレイングゲームです。
前作『ファイナルファンタジーVII』の世界的成功を受けて開発された本作は、シリーズ8作目にしてさらなる技術的進化を遂げ、リアル志向のグラフィック表現や、恋愛をテーマに据えたストーリー展開が話題となりました。
物語の舞台は、魔法と軍事力が均衡する世界。
プレイヤーは傭兵養成学校「バラムガーデン」に所属する青年スコール・レオンハートとして、仲間たちと共に国際的な紛争に巻き込まれながら、やがて時間を超えた壮大な陰謀と魔女との戦いに挑むことになります。
スコールは内向的で孤独を恐れる性格ながらも、作中で出会う少女リノアとの交流を通じて、徐々に心を開き、変化していく姿が丁寧に描かれています。
ファイナルファンタジーVIIIでは従来のレベル制成長システムや装備品の概念が大胆に見直され、「ジャンクション」システムが導入されました。
魔法を「ドロー」してストックし、それを召喚獣(ガーディアンフォース)と結びつけることで能力値を強化するという斬新なシステムは、プレイヤーに高度な戦略性と自由度をもたらしました。
またバトル中の演出や召喚獣のグラフィックもよりダイナミックになり、当時のハード性能を最大限に活かした内容となっています。
グラフィック面では前作のデフォルメ調から一転し、人物キャラクターの等身がリアルに描かれるようになったことにより、ドラマ性のある演出がさらに際立ちました。
イベントシーンはフルCGムービーとリアルタイム映像がシームレスに融合し、まるで一本の映画を見るかのような臨場感を生み出しています。
音楽は引き続き植松伸夫が担当しており、主題歌「Eyes On Me」は中国系シンガーのフェイ・ウォンが歌い、日本のゲーム音楽としては初めて商業的なシングルリリースが行われました。
オーケストラ調のサウンドと物語の情感が見事に重なり合い、ファイナルファンタジーシリーズにおける音楽の重要性をさらに高めた作品とも言えます。
本作は全世界でも900万本以上を売り上げ、商業的にも大きな成功を収めました。
システム面での挑戦、映像表現の進化、そして人間関係を中心に据えた物語構成は、従来のRPGに対する価値観を覆すものであり、ファイナルファンタジーVIIIはシリーズの中でも異色ながらも非常に高い評価を受けている作品です。
時代を超えて語り継がれるその完成度の高さと独創性は、今なお多くのファンを魅了し続けています。
3位:ファイナルファンタジーIX(PS)・・・280万本
| タイトル | ファイナルファンタジーIX |
| ゲームハード | PlayStation |
| 発売日 | 2000年7月7日 |
| 国内販売数 | 280万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で3番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーIX』です。
国内販売数は約280万本となっています。
ファイナルファンタジーIXは2000年7月7日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)からプレイステーション向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第9作目にあたる本作はグラフィックや演出の進化が続く中で、あえてシリーズ原点への回帰を掲げ、「クリスタル」や中世ファンタジー調の世界観を前面に押し出した、クラシカルな魅力にあふれる作品として位置づけられています。
物語は空を飛ぶ海賊船「プリマビスタ号」に乗り込んだ盗賊団タンタラスが、アレクサンドリア王国の王女ガーネットを誘拐するところから始まります。
しかし王女は自らの意思で王国を出ようとしており、タンタラスの少年ジタンと共に旅に出ることを望んでいました。
やがて彼らは黒魔導士のビビや騎士スタイナーらと出会い、それぞれの運命を背負いながら、世界の真理と自らの存在に関わる壮大な冒険へと巻き込まれていきます。
本作では前作までの近未来的で写実的なビジュアル表現とは異なり、キャラクターのデフォルメを強調した温かみのあるデザインが採用されました。
背景は緻密に描かれた絵画的なプリレンダリング画像を使用し、まるで絵本の中のような幻想的で奥行きのある世界を構築しています。
また種族や文化の多様性が物語の随所に表れており、登場人物たちの関係性や成長が物語の大きな軸となっています。
バトルシステムはシリーズ伝統のATB(アクティブ・タイム・バトル)を踏襲しつつ、「アビリティ」や「トランス」といった独自の成長要素が盛り込まれています。
装備品に応じてアビリティを習得するシステムは、キャラクター育成に戦略的な幅を持たせる一方、シリーズ経験者には懐かしさをもたらす要素でもあります。
ジョブの個性も明確に表現されており、キャラクターごとの役割がより強調された点も特徴的です。
音楽は植松伸夫が単独で全曲を手がけ、シリーズの中でも特に評価が高い作品のひとつです。
「その扉の向こうに」「独りじゃない」「ビビのテーマ」など、登場人物の心情や場面の空気を繊細に表現する楽曲群は、物語と密接に結びつき、プレイヤーの記憶に深く刻まれました。
古き良きRPGの情緒と、現代的な表現との融合を音楽面でも実現しています。
ファイナルファンタジーIXは世界中で500万本以上を売り上げ、プレイステーション時代の集大成ともいえる作品として高く評価されています。
ファンタジー世界の温かさ、キャラクターの人間味、そして命や存在の意味を問いかける哲学的なテーマが、多くのプレイヤーの心を打ちました。
シリーズの原点回帰でありながら今なお色褪せない魅力を持つ作品として、長年にわたり愛され続けています。
4位:ファイナルファンタジーX(PS2)・・・273万本
| タイトル | ファイナルファンタジーX |
| ゲームハード | PlayStation2 |
| 発売日 | 2001年7月19日 |
| 国内販売数 | 273万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で4番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーX』です。
国内販売数は約273万本となっています。
ファイナルファンタジーXは2001年7月19日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)からプレイステーション2向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第10作目にあたる本作は、シリーズ初のフルボイス対応や3D空間での自由なカメラワーク、そして美麗な映像表現によって、プレイステーション2の性能を最大限に活かした革新的な作品として高く評価されています。
物語の舞台は異世界スピラ。
ブリッツボールの天才選手ティーダは、突如現れた謎の存在「シン」によって、彼の住む大都市ザナルカンドから未知の世界へと飛ばされてしまいます。
そこで彼は召喚士ユウナと出会い、世界を脅かす「シン」を倒すための巡礼の旅に同行することになります。
旅を通じて絆を深めていく仲間たちとの交流、ユウナに課せられた過酷な運命、そしてティーダ自身の出自と世界の真実が徐々に明かされていきます。
ファイナルファンタジーXでは、戦闘システムに「CTB(コンディショナル・ターン・バトル)」が導入され、リアルタイム要素を排し、ターンの順番が戦略的に可視化される仕組みとなりました。
またキャラクターの成長は従来のレベル制ではなく「スフィア盤」と呼ばれる独自のボード型システムで行われ、自由度の高い育成が可能です。
それぞれのキャラクターには明確な役割が与えられており、戦闘中に入れ替えることで多彩な戦略を練ることができます。
グラフィック面ではプレイステーション2の性能を活かしたリアルタイム3D表現が施され、キャラクターの細かな表情や自然描写、建築物の美しさなどが高い臨場感をもって描かれています。
さらにシリーズ初のフルボイス化によって、登場人物たちの感情表現に奥行きが生まれ、ストーリーへの没入感が飛躍的に向上しました。
イベントシーンではフルCGムービーも多用され、映像作品としての完成度も極めて高いものとなっています。
音楽は植松伸夫を中心に、浜渦正志、仲野順也ら複数の作曲家が手がけており、シリーズの新たな方向性を感じさせるサウンドが展開されました。
中でもオープニングを飾る「ザナルカンドにて」は、静かで切ない旋律が多くのプレイヤーの心を掴み、ファイナルファンタジーの代表的な楽曲として語り継がれています。
またユウナの儀式シーンなどで流れる「素敵だね」も、物語を象徴するテーマ曲として人気を博しました。
本作は全世界で1000万本以上を売り上げ、シリーズの中でも屈指の人気を誇る作品となりました。
感動的なストーリー展開、個性的で魅力的なキャラクター、そして斬新なシステムと美麗な演出が融合したファイナルファンタジーXは、家庭用ゲームの新たな表現力を切り拓いた金字塔的存在であり、多くのファンの記憶に深く刻まれています。
その後もリマスター版や続編『ファイナルファンタジーX-2』が展開されるなど、今なお根強い人気を持つタイトルです。
5位:ファイナルファンタジーV(SFC)・・・245万本
| タイトル | ファイナルファンタジーV |
| ゲームハード | スーパーファミコン |
| 発売日 | 1992年12月6日 |
| 国内販売数 | 245万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で5番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーV』です。
国内販売数は約245万本となっています。
ファイナルファンタジーVは1992年12月6日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)からスーパーファミコン向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第5作目にあたる本作は、自由度の高い「ジョブチェンジシステム」の進化形である「アビリティシステム」を採用し、戦術の多様性とキャラクター育成の奥深さで高く評価されました。
物語はクリスタルの力によって平和が保たれていた世界を舞台に、風の異変をきっかけとして動き出します。
主人公バッツは、隕石の落下現場で出会った王女レナ、記憶を失った老人ガラフ、そして女海賊ファリスと共に、砕けゆくクリスタルを守るための旅に出ます。
彼らはやがて、異世界から復活しようとする暗黒の存在エクスデスとの戦いに巻き込まれ、世界の存亡をかけた壮大な冒険へと発展していきます。
本作の大きな特徴は前作までのジョブシステムをさらに進化させた「ジョブとアビリティの組み合わせ」です。
プレイヤーはキャラクターに自由にジョブ(職業)を与え、バトルやイベントを通じてアビリティを習得することができます。
そして一度習得したアビリティは、他のジョブでも自由に組み合わせることができるため、戦略の幅が非常に広がりました。
このシステムによって回復魔法を使えるナイトや、黒魔法を操るモンクといった個性的な育成が可能となり、プレイヤーごとに異なる戦術を楽しむことができます。
バトルシステムは、前作に続いて「アクティブ・タイム・バトル(ATB)」を採用。
リアルタイムで進行するバトルにおいて、素早さや技の選択によって戦局が変わる緊張感が生まれました。
またボス敵のギミックや状態変化に対して、アビリティを活かした柔軟な対応が求められる場面も多く、戦術性の高いバトルが展開されます。
グラフィックはスーパーファミコンの限界を感じさせないほど緻密で、ファンタジー色の強い背景やキャラクターのアニメーションが物語に彩りを加えています。
音楽は植松伸夫が全曲を担当しており、「ビッグブリッヂの死闘」「親愛なる友へ」「遥かなる故郷」など、ゲーム音楽史に残る名曲が多数収録されています。
特に「ビッグブリッヂの死闘」は、本作の人気キャラクター「ギルガメッシュ」の登場と共に強く印象づけられ、多くのシリーズ作品でも引用される代表的な楽曲となりました。
ファイナルファンタジーVは、国内外で高い評価を受けた作品であり、後年にはプレイステーション版やゲームボーイアドバンス版、スマートフォン版など複数の機種に移植されています。
洗練された育成システムと重厚な冒険譚、そして個性豊かなキャラクターたちが織りなすドラマは、シリーズの中でも特に自由度の高い戦略性を好むファンに支持されており、今なお根強い人気を誇る一作です。
6位:ファイナルファンタジーXII(PS2)・・・223万本
| タイトル | ファイナルファンタジーXII |
| ゲームハード | PlayStation2 |
| 発売日 | 2006年3月16日 |
| 国内販売数 | 223万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で6番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーXII』です。
国内販売数は約223万本となっています。
ファイナルファンタジーXIIは2006年3月16日にスクウェア・エニックスからプレイステーション2向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第12作目にあたる本作は、従来のコマンド式バトルを刷新し、シームレスなフィールドとリアルタイム制の戦闘を融合させた新たなシステムを導入することで、シリーズの中でも特に革新的な位置づけを持つ作品となりました。
物語の舞台は、広大な大地と空に浮かぶ艦隊が交差する世界「イヴァリース」。
大国アルケイディア帝国による侵略によって祖国ダルマスカを失った少年ヴァンは、空賊に憧れる孤児です。
ある日王女アーシェの生存をきっかけに、彼は空賊バルフレアとその相棒フラン、元将軍バッシュらと出会い、帝国の陰謀と古代の秘術「覇王の力」を巡る大いなる戦いへと巻き込まれていきます。
壮大な国家間の政治劇と、それに翻弄されながらも自らの意志で未来を選ぼうとする若者たちの姿が、重厚なストーリーとして描かれます。
本作では、「ガンビットシステム」と呼ばれる新たな戦闘システムが導入されました。
これは、プレイヤーが事前に条件と行動を設定することで、キャラクターが自動で行動するシステムです。
たとえば「HPが50%未満の味方にケアル」や「敵が近づいたら攻撃」といった指令を組み合わせることで、戦況に応じた柔軟な戦闘が可能となります。
これにより戦闘はより戦略的かつスピーディに展開し、従来のRPGの枠を超えた独自のプレイ感覚を実現しています。
さらに、キャラクターの育成は「ライセンスボード」によって行われます。これにより、武器の使用や魔法の習得など、個々の成長方針をプレイヤーが自由に決定できます。後年のリマスター版では「ゾディアックジョブシステム」が採用され、ジョブの選択肢が明確化されたことで、より戦略的で多様なパーティ編成が可能となりました。
グラフィック面では、プレイステーション2の性能を最大限に活かした広大で美麗なフィールド、緻密なキャラクターモデル、そして壮大な建築物や空中艦隊の描写が高く評価されました。
ロード時間の短さやシームレスなマップ移動も、ゲーム体験の快適さに大きく貢献しています。
音楽は崎元仁が手がけ、荘厳でオーケストラ調の楽曲が世界観を支え、従来のシリーズとは異なる重厚な雰囲気を作り上げています。
ファイナルファンタジーXIIは、発売当初から高い評価と注目を集め、国内外で600万本以上を売り上げました。
その後のリマスター版『ファイナルファンタジーXII ザ ゾディアック エイジ』では、グラフィックの高解像度化や高速モードの追加、BGMのアレンジなどが施され、現代のプレイヤーにも再評価されています。
従来のファンタジーRPGに革新をもたらした本作は、シリーズの中でも特に挑戦的で完成度の高いタイトルとして、多くのファンに支持され続けています。
7位:ファイナルファンタジーX-2(PS2)・・・211万本
| タイトル | ファイナルファンタジーX-2 |
| ゲームハード | PlayStation2 |
| 発売日 | 2003年3月13日 |
| 国内販売数 | 211万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で7番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーX-2』です。
国内販売数は約211万本となっています。
ファイナルファンタジーX-2は2003年3月13日にスクウェア(当時)からプレイステーション2向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ナンバリングタイトルとしてはシリーズ初の直接的な続編であり、前作『ファイナルファンタジーX』の世界「スピラ」を舞台に、物語のその後を描いています。
また、シリーズとしては初めて女性キャラクター3人のみを操作するパーティ構成が採用され、よりスタイリッシュかつスピーディなゲームデザインが特徴的な作品です。
物語の主人公は、前作にも登場した召喚士ユウナ。
シンの消滅とともに訪れた「永遠のナギ節」と呼ばれる平和な時代を迎えたスピラでしたが、新たな思想の対立や、過去の遺産を巡る争いが表面化しつつありました。
そんな中ユウナは「スフィアハンター」として行動を始め、リュックやパインと共に「カモメ団」と呼ばれる旅のチームを結成します。
やがてある映像スフィアに映った人物の姿が、ユウナの心に再び火を灯し、世界の過去と未来に関わる新たな冒険が幕を開けます。
ゲームシステムは、従来の「ジョブチェンジ」に当たる「ドレスフィア」システムが導入され、バトル中に衣装(役割)をリアルタイムで切り替えながら戦うというダイナミックなスタイルが実現されています。
ドレスごとにスキルや能力が異なり、戦況に応じて瞬時に役割を変更することで、戦略的でテンポの良い戦闘が可能です。
さらに戦闘システムにはシリーズでおなじみのアクティブ・タイム・バトル(ATB)が再び採用され、スピーディかつ爽快なバトル展開が楽しめる構成となっています。
前作の重厚なドラマ性や荘厳な雰囲気とは対照的に、本作はポップで軽快な演出が随所に散りばめられており、明るくコミカルなシーンとシリアスな展開が混在するバランスが特徴です。
一方で、スピラの過去に秘められた戦争や悲劇、そして失われた人々の想いが描かれることで、物語には深みも加わっています。
プレイヤーの選択や達成度によってエンディングが分岐するマルチエンディング方式も採用されており、自由度の高いプレイが可能です。
音楽はシリーズの音楽を長年支えてきた植松伸夫に代わり、松枝賀子と福井健一郎が新たに担当。
従来のファイナルファンタジーとは一線を画すエレクトロニカやポップス寄りの楽曲が多く採用されており、ユウナ役の声優・青木麻由子が歌うオープニングテーマ「real Emotion」やエンディング曲「1000の言葉」は、ゲームの世界観を象徴する存在となっています。
ファイナルファンタジーX-2は前作『X』とは異なるテイストと構造を持ちながらも、スピラという世界をより掘り下げ、登場人物たちのその後を描くことで、プレイヤーに新たな視点と感動をもたらしました。
商業的にも国内外で大きな成功を収め、ファイナルファンタジーシリーズにおける続編作品の可能性を切り拓いた意欲作として、今なお多くのファンに親しまれています。
8位:ファイナルファンタジーXIII(PS3)・・・187万本
| タイトル | ファイナルファンタジーXIII |
| ゲームハード | PlayStation3 |
| 発売日 | 2010年12月17日 |
| 国内販売数 | 187万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で8番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーXIII』です。
国内販売数は約187万本となっています。
ファイナルファンタジーXIIIは2010年12月17日にスクウェア・エニックスからプレイステーション3向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第13作目にあたる本作は、シリーズ初のHD機専用タイトルとして開発され、美麗なグラフィック、映画的な演出、そして高速かつ戦略的なバトルシステムによって、新世代RPGの到達点を目指した意欲作です。
物語の舞台は天空に浮かぶ人工都市「コクーン」と、下界に広がる未開の大地「パルス」。
人々は「ファルシ」と呼ばれる超常的な存在に管理されて暮らしており、ある日、パルス由来のファルシが発見されたことで、住民たちは「パージ(強制追放)」の名の下に、政府により過酷な処分を受けようとしていました。
そんな中主人公ライトニングは、妹セラを救うために政府に反旗を翻し、やがて運命に翻弄される6人の「ルシ」としての戦いを開始します。
彼らは「ファルシ」に選ばれたことで特別な力を得る代わりに、定められた使命「フォーカス」を果たさねば「シ骸」と化すという過酷な宿命を背負わされており、それぞれの葛藤と絆が物語の中核を成します。
バトルシステムには、「オプティマチェンジ」と呼ばれる独自の仕組みが導入されました。
これはバトル中にパーティ全体の役割(ロール)を一瞬で切り替えることで、攻撃・防御・回復などのバランスを戦況に応じて調整できるシステムです。
プレイヤーは基本的にリーダーキャラクター1人を操作し、他のメンバーはAIが自動的に行動しますが、適切なタイミングでのオプティマ切り替えが攻略の鍵を握ります。
バトルは非常にテンポが速く、連携攻撃や「チェーン」「ブレイク」といった概念も加わり、従来のターン制RPGを再構築したような爽快感と緊張感を味わうことができます。
育成面では「クリスタリウム」と呼ばれるシステムが採用されており、バトルで得たポイントを使って能力を強化し、各キャラクターの役割に応じた成長が可能です。
ステージクリア型で進行するストーリー構成も特徴的で、序盤から中盤にかけては一本道の展開が続く一方、後半では広大なフィールド「グラン=パルス」に到達し、ミッションやモンスター討伐など自由度の高いプレイも可能になります。
グラフィック面では、スクウェア・エニックス独自の「クリスタルツールズ」エンジンにより、キャラクターの細かな表情、自然環境、都市のディテールまで緻密に描写され、プレイステーション3のハード性能を最大限に活かした高品質な映像が実現されています。
ムービーとゲームパートが滑らかにつながる演出も、シリーズの映画的表現をさらに進化させました。
音楽は、浜渦正志がメインコンポーザーとして全体を手がけ、クラシック、電子音楽、オーケストラを融合させた豊かなサウンドが作品の世界観を支えています。
テーマ曲「君がいるから」は、物語の中心にある「大切な人との絆」という感情を象徴する存在として、多くのプレイヤーの心に残る一曲となりました。
ファイナルファンタジーXIIIは、世界観・システム・映像・音楽のすべてにおいて新たな表現を追求した作品であり、国内外で600万本以上の販売を記録しました。
その後は直接的な続編である『ファイナルファンタジーXIII-2』および『ライトニングリターンズ ファイナルファンタジーXIII』へと物語が続き、「ファブラ・ノヴァ・クリスタリス」という神話体系に基づく三部作が形成されました。
挑戦と革新に満ちた本作は、HD世代のファイナルファンタジーの幕開けを告げる記念碑的作品として、今なお語り継がれています。
9位:ファイナルファンタジーXV(PS4・Xbox One)・・・147万本
| タイトル | ファイナルファンタジーXV |
| ゲームハード | PS4、Xbox One |
| 発売日 | 2016年11月29日 |
| 国内販売数 | 147万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で9番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーXV』です。
国内販売数は約147万本となっています。
ファイナルファンタジーXVは2016年11月29日にスクウェア・エニックスからプレイステーション4およびXbox One向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第15作目にあたる本作は、長期にわたる開発期間を経て完成した大作であり、従来のシリーズとは一線を画す「オープンワールド」「リアルタイムアクションバトル」「ブロマンス(男同士の絆)」といった新たな要素を前面に押し出し、現代的なFF像を提示する挑戦的な作品となりました。
物語の舞台は、神話と科学が共存する世界「イオス」。
この世界ではルシス王国が神聖なるクリスタルを護る一方、ニフルハイム帝国が周辺諸国を次々と制圧し、戦争が激化していました。
そんな中ルシス王子ノクティスは、幼なじみで婚約者でもあるオルティシエの令嬢ルナフレーナとの政略結婚のため、幼なじみの親友たち――グラディオラス、イグニス、プロンプトと共に旅へと出発します。
だがその矢先、帝国によって王都が陥落し、父王レギスが命を落としたとの報が届きます。
王子としての運命を背負いながら、ノクティスは仲間たちと共に、真の王となるための試練と世界の命運をかけた戦いに挑んでいきます。
本作の最大の特徴は、シリーズ初の本格的なオープンワールドを採用している点です。
美麗な自然環境や街並みがシームレスに広がり、プレイヤーは広大なマップを自由に探索することができます。
クルマ「レガリア」を使ったドライブ旅行、キャンプでの宿泊、釣りや料理といった多彩なサブコンテンツも用意されており、旅そのものがひとつの体験として深く味わえる構成になっています。
戦闘システムは、従来のコマンドバトルから一新された「アクティブクロスバトル(ACB)」を採用し、プレイヤーはノクティスを直接操作してリアルタイムで攻撃や回避、ワープ移動、仲間との連携技を駆使して戦います。
武器や魔法、召喚獣の使用もスピーディかつダイナミックで、アクションゲームとしての手応えとRPGとしての戦略性を両立させています。
また、バトル中の仲間との掛け合いやサポート行動が、絆や成長を実感させる演出として活かされています。
育成要素には「アストラルスフィア」というスキルツリー方式が採用され、バトル・探索・サバイバルなど様々なプレイスタイルに応じてキャラクターを強化することができます。
旅を共にする仲間たちも、バトル以外の場面で料理・撮影・サバイバル・釣りといった特技を持ち、それぞれの個性が旅の中で活きる仕組みが設けられています。
音楽は下村陽子がメインコンポーザーを務め、壮大でドラマチックな旋律と繊細なピアノ曲、そしてシリーズ過去作の楽曲も車内BGMとして流せるなど、過去と現在の融合が図られています。
物語終盤には、「Stand by Me」(Florence + the Machineによるカバー)が感動的に使用され、物語の情緒を一層際立たせています。
ファイナルファンタジーXVは、開発当初は『ファイナルファンタジー ヴェルサスXIII』として発表された経緯もあり、実に10年以上にわたる開発期間を経て完成したタイトルです。
発売後も有料・無料を含む多くのアップデート、キャラクター別の追加エピソード、オンライン拡張版『FFXV:戦友』、小説『The Dawn of the Future』などが展開され、長期的に物語の補完と再構築が続けられました。
世界中で1000万本以上の販売を記録した本作は、シリーズの新たな方向性を示すとともに、「旅」「友情」「別れ」といった普遍的なテーマを映像と音楽、インタラクティブな演出で描き切った意欲作です。
ファイナルファンタジーXVは、現代におけるファンタジーRPGの可能性を広げた、記憶に残る一篇の旅路として、多くのファンの心に深く刻まれています。
10位:ファイナルファンタジーIV(SFC)・・・144万本
| タイトル | ファイナルファンタジーIV |
| ゲームハード | スーパーファミコン |
| 発売日 | 1991年7月19日 |
| 国内販売数 | 144万本 |
ファイナルファンタジーシリーズの内、国内で10番目に売れた作品は『ファイナルファンタジーIV』です。
国内販売数は約144万本となっています。
ファイナルファンタジーIVは1991年7月19日にスクウェア(現スクウェア・エニックス)からスーパーファミコン向けに発売されたロールプレイングゲームです。
ファイナルファンタジーシリーズの第4作目にあたる本作は、グラフィックやシステムの進化はもちろん、ドラマ性の強いストーリーテリングと個性豊かなキャラクターたちによって、シリーズの方向性を決定づけた重要な転換点とされています。
物語の主人公は、バロン王国の飛空艇部隊「赤い翼」を率いる暗黒騎士セシル。
王の命令に疑問を抱きながらも任務をこなしていた彼は、無抵抗の民からクリスタルを奪うという非道な行為に心を痛め、やがて騎士団長の地位を剥奪されてしまいます。
セシルは自らの罪と向き合いながら旅に出て、白魔道士ローザ、親友のカイン、黒魔道士リディアなど多くの仲間たちと出会い、世界を脅かす黒幕ゴルベーザ、さらには月から来た異星の存在との戦いへと発展していきます。
本作では感情や成長を描くストーリードリブンな展開が大きな魅力となっており、裏切り、贖罪、別れ、そして希望といった重厚なテーマが濃密に描かれます。
セシルが物語中盤で「暗黒騎士」から「パラディン」へと転職し、自らの過去を乗り越えていく象徴的なシーンは、シリーズでも屈指の名場面として語り継がれています。
戦闘システムには、シリーズ初となる「アクティブ・タイム・バトル(ATB)」が導入されました。
これは、従来のターン制にリアルタイム要素を加えたもので、キャラクターの行動ゲージが時間と共に溜まり、順次コマンドを入力するという画期的な方式です。
このシステムはその後のファイナルファンタジー作品にも継承され、RPGの戦闘システムにおける革新として大きな影響を与えました。
また、プレイヤーが自由にジョブを変更することはできず、各キャラクターが固有の職業やアビリティを持っている点も特徴です。
これにより物語と戦闘が密接に結びつき、それぞれのキャラクターの役割や成長がよりドラマチックに描かれています。
仲間が入れ替わる展開も多く、そのたびに戦略を見直す必要があるため、プレイヤーには常に新鮮な体験が求められます。
音楽は植松伸夫が担当し、「愛のテーマ」「バトル2」「赤い翼」など、ゲーム音楽史に残る名曲が多数収録されています。
特に「テーマ・オブ・ラブ」は感動的な旋律で多くのファンに親しまれ、日本では中学校の音楽教材に採用されたこともありました。
音楽と物語の融合が高い完成度で実現されている点も、本作の評価を高めています。
ファイナルファンタジーIVは国内外で高い評価を受け、その後もプレイステーション、ゲームボーイアドバンス、ニンテンドーDS、スマートフォン、さらには高解像度でのリメイク作品が発売されるなど、長年にわたり愛され続けています。
シリーズ初の本格的なドラマ重視の構成と、新しい戦闘システムの導入によって、ファイナルファンタジーIVは、RPGの表現力と物語性を大きく前進させた記念碑的作品として、今なお多くのファンに語り継がれる名作です。
まとめ
いかがだったでしょうか。
この記事では、歴代ファイナルファンタジーシリーズの国内売上販売数ランキングトップ10をご紹介しました。
ここまでお読みいただきありがとうございました。
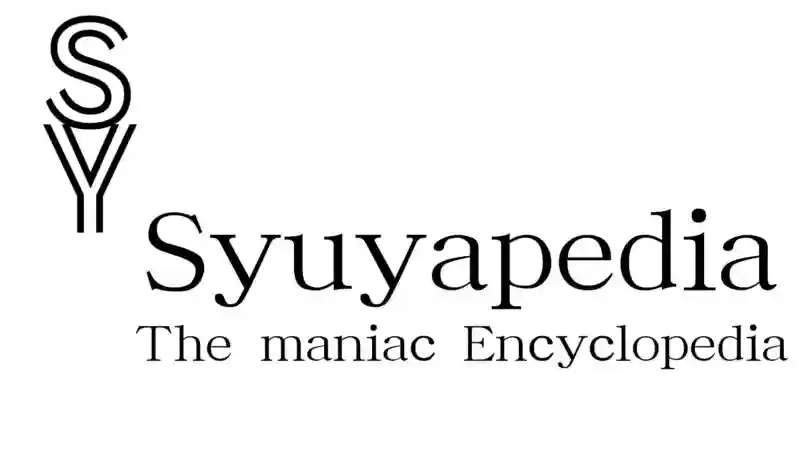




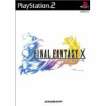

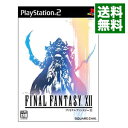
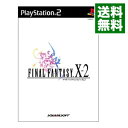



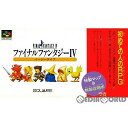


コメント