中国語の基本中の基本フレーズである10フレーズがわかります。
你好!我是秋也!
みなさんこんにちは、syuyaです。
色々と世界の注目を集める、東アジアの超大国中華人民共和国。
その中国で話されている中国語は、世界で13億9000万人が母語として使用する、世界で最も話者が多い言語です。
第二言語としても2億人が話し、また国連の定める6つの国連公用語の一つでもあります。
また日本を訪れる中国人の数も増加し続けており、2019年の訪日中国人の人数は9,594,394人にも及びました。
これは、日本で二番目に人口が多い神奈川県の、2022年の人口である9,232,794人を超えています(!!!)
凄まじいですよね。
ですがそういった意味合いからも、中国語を学ぶ価値というものは高まっています。
日本と同じく漢字を使用する国であるので、例えば漢字を使用しない西洋人などと比べて、漢字を学ぶ際のアドバンテージがあるのも魅力です。
みなさまも中国語を学ぶ事に挑戦してみてはいかがでしょうか?
広い地域で話され、多様な民族に話されている中国語には、北京語、広東語、福建語など、地域によって大きく違うのが特徴です。
ですから同じ中国語話者であっても、方言の違いによって全く意思疎通が取れないという事もざらにあるそうです。
この記事では、そんな中国語の中でもメジャーと言える北京語をベースに、中国語の基礎フレーズをご紹介します。
こんにちは・・・你好(ニイハオ)

你好(ニイハオ)
ピンイン nǐ hǎo
まずご紹介するのは、代表的な中国語の挨拶である『你好(ニイハオ)』です。
”你(ニィ)”が”あなた”、”好(ハオ)”が”良い”という意味になります。
発音はピンインで「nǐ hǎo」と表記され、どちらも第三声ですが、自然な会話の中では声調の変化が起こり、「ní hǎo」となるのが一般的です。
これは声調のルールによる変化で、第三声が二つ続くとき、最初の第三声が第二声に変化するためです。
主に挨拶する相手の立場が対等か、自分より下の誰か一人に対して使われます。
これが挨拶する相手が目上の人の場合は、
『您好 Nín hǎo(ニンハオ)』
となります。
そして、相手が複数の場合は、
『你们好 Nǐ mén hǎo (ニーメンハオ)』
となります。
使用場面としては、初対面の相手や改まった挨拶のときに使われるのが基本ですが、日常的な「やあ」「どうも」といった軽い挨拶としても使われることがあります。
また、時間帯によって『早上好(おはよう)』『晚上好(こんばんは)』といった挨拶に言い換えることもできますが、どんな時間帯でも無難に使える『你好』は非常に便利な表現となっています。
元気ですか?・・・你好吗?(ニィ ハオ マ?)

你好吗?(ニイハオマ?)
ピンイン Nǐ hǎo ma
相手の体調を尋ねるのは、万国共通のあいさつと言えます。
”お元気ですか?”と尋ねる時は、”こんにちは”を意味する中国語である”你好”に疑問語である”吗”をつけ、”你好吗”とするだけです。
大変わかりやすいですね。
これを言われた場合、調子が良い時には、
『很好 hěn hǎo (ヘンハオ)』
と返答します。
また、調子が良くない時は、
『不好 bù hǎo(プゥ ハオ)』
と答えます。
このように、相手の調子を尋ねる際のフレーズとして有名な『你好吗?』ですが、実際の中国語の会話ではやや教科書的な表現とされることがあり、ネイティブ同士ではあまり頻繁には使われません。
代わりに
『最近怎么样? zuì jìn zěn me yàng?(最近どう?)』
『你还好吧? nǐ hái hǎo ba?(大丈夫?)』
など、より自然な表現が使われることが多いです。
ありがとう・・・谢谢(シェ シェ)

谢谢 (シェシェ)
ピンイン Xièxiè
続いては感謝の意を表す表現である『谢谢 Xièxiè(シェシェ)』です。
「谢」は日本の漢字で表すと「謝」であり、「感謝」の「謝」と考えると、大変分かりやすいですね。
中国語ではこの文字を2回繰り返すことで、感謝の意を表す言葉となります。
発音は「xièxie(シエシエ)」で、どちらも第4声(高くて下がる調子)です。
ただし、実際の会話では2つ目の「谢」の声調は軽声(qīngshēng)になり、「xièxie(xiè・xie)」のように、2音目を軽く短く発音するのが自然です。
「谢谢」と言われた際は、日本語における”どういたしまして”にあたる、
”不客气 Bú kè qi (プゥ クゥァ チー)”
または、
”别客气 Bié kè qi (ビェ クゥァ チー)”
などと返すのが良いでしょう。
どちらも”いいよ、気にしないで”といったニュアンスです。
すみません・・・对不起(トゥイ プ チー)

对不起(トゥイ プ チー)
ピンイン duìbuqǐ
続いては、代表的な謝罪の表現である『对不起 duìbuqǐ(トゥイ プ チー)』です。
『对(duì)』は「~に対して」、『不起(bu qǐ)』は「起こせない/立ち上がれない」という意味を持ち、直訳すると「相手の気持ちに応えられない」というニュアンスになります。
つまり、「あなたに対して申し訳ないことをした」という意味合いです。
発音は「duì bu qǐ」で、「对」は第4声(高くて下がる調子)、「不」は軽声に近い形で読みますが、通常は第4声で覚え、「起」は第3声(低く沈んで上がる調子)です。
フォーマルな謝罪の言葉であり、これとは別に道でぶつかってしまった時などに軽めの謝罪をするときには、
『不好意思 bù hǎoyìsi (プゥ ハオ イース)』
を使います。
私の名前は~です。・・・我 叫 ~(ウォ ジャオ ~)

我 叫 ~(ウォ ジャオ ~)
ピンイン wǒ jiào
中国語で”私の名前は~です。”と言う場合は、『我 叫 ~ wǒ jiào (ウォ ジャオ ~)』と言います。
日本語で”叫”という漢字は、”大きな声で叫ぶ”などといった時に使われる漢字ですが、中国語における”叫”は上記のように名前を名乗る時の他に、”~を呼ぶ”や、”(人に)~させる”など、様々な意味がある漢字となっています。
このように、同じ漢字でも中国語と日本語では意味が異なるものも多くあります。
他に、姓だけ名乗りたいときは、
『我 姓 ~ wǒ xìng (ウォ シン ~)』と言います。
こちらは日本語の”姓”と同じ意味の漢字なので、わかりやすいですね。
中国人に最も多い苗字は”李”さんで、次いで”王”、”張”、”劉”、”陳”、”楊”、”黄”、”趙”、”周”、”呉”という苗字が多いそうです。
私は~才です。・・・我 ~ 岁(ウォ ~ スイ)

我 ~ 岁 (ウォ ~ スイ)
ピンイン Wǒ ~ suì. 3声+4声
中国語で年齢を教える言葉は『我 ~ 岁 Wǒ ~ suì. (ウォ ~ スイ)(~には年齢の数字)』と言います。
例えば”私は20才です”という場合、
『我二十岁 Wǒ èrshí suì(ウォ アールシー スイ)』
となります。
”岁”とは、日本語の漢字でいう所の”才”または”歳”です。
”わたし”を意味する”我”にそのまま”~才”を意味する”~岁”をつける事で、簡単に年齢を教える表現に出来るんですね。
また、中国語における数詞は非常にシンプルで、
| 数字 | 中国語 | 読み方 |
| 1 | 一(yī) | イー |
| 2 | 二(èr) | アール |
| 3 | 三(sān) | サン |
| 4 | 四(sì) | スー |
| 5 | 五(wǔ) | ウー |
| 6 | 六(liù) | リウ |
| 7 | 七(qī) | チー |
| 8 | 八(bā) | パー |
| 9 | 九(jiǔ) | ジウ |
| 10 | 十(shí) | シー |
の1~10までの数詞を使う事によってあらわすことが出来、例えば11ならば『十一(shí yī)』、20ならば『二十(èr shí)』、21ならば『二十一(èr shí yī)』と表すことが出来ます。
私の仕事は~です。・・・我 的 工作 是 ~( ウォ ダ ゴンツォ シ ~)

我 的 工作 是 ~ (ウォ ダ ゴンツォ シ ~)
ピンイン Wǒ de gōngzuò shì
中国語で職業を教える際には『我 的 工作 是 ~ Wǒ de gōngzuò shì ~ ( ウォ ダ ゴンツォ シ ~)』と言います。
『我的』が「私の」、『工作』が「仕事」、『是』が「~です」という意味で、シンプルに「わたしの仕事は~です。」という構造となっています。
主な職業の中国語の名称は、
会社員=公司职员
公務員=公务员
教師=老师
警察官=警察
医師=医生
フリーター=飞特族
学生=学生
と言います。
これらの語句を『我 的 工作 是 ~』の”~”の部分に入れれば、文が完成します。
中国人の仕事観としては、日本人に比べて結果主義的であると言われています。
また中国人に人気の職業としては医者や教師、エンジニアなどのIT関係職が人気の職業であり、特にIT関係職は近年のIT技術発展に伴ってより人気の職業となることが予想されています。
はい・・・是(シィ)

是 (シィ)
ピンイン shì
中国語で”Yes”を表わすときは『是 shì (シィ)』で表します。
他に肯定を表す語句としては、
『對 duì (ドゥイ)』
『沒錯 méi cuò (メイ ツォ)』
などがあります。
いいえ(No)・・・不是(プゥ シィ)

不是(プゥ シィ)
ピンイン búshì
中国語で”No”を表わす言葉は、”Yes”を表わす『是』の前に否定を表す『不 bú (プゥ)』をつけるだけです。
極めて簡単ですね。
このように、中国語で否定を表わすときは『不』か、『没 méi(メイ)』をつければ良いのです。
どちらを使うかは、否定する単語の種類や時制などによって変化します。
さようなら・・・再见(サイ ツェン)

再见(サイ ツェン)
ピンイン zài jiàn
中国語で”さようならは『再见 zài jiàn (サイ ツェン)』と言います。
『再』は「もう一度」や「再び」、『见』は「会う・見る」という意味があり、直訳すると「また会う」という意味合いになります。
つまり、「また会いましょう」という前向きな別れの言葉です。
再び会う事を前提としていますが、そうでなくとも広く使用される別れの挨拶です。
発音は”zài jiàn”で、どちらも第4声(高くてストンと落ちる調子)です。
ハッキリ発音すると、丁寧かつ自然な印象になります。
また後で会う時は
『一会儿见 Yīhuì’er jiàn(イー フイアーゥ ジェン)』
”また明日”という時は、
『明天见 Míngtian jiàn ( ミンティエン ジェン)』
となります。
若い人たちの間では、英語の”byebye”から輸入された
『拜拜 Bàibai(バイバイ)』
も良く使用されています。
中国語を学ぶ際のおすすめ書籍
ここからは中国語を学ぶ際のお勧めの参考書をご紹介します。
参考書によって、レベルや学べる内容が異なりますので、ご自身の目的に合った参考書を選ぶ事をお勧めします。
新ゼロからスタート中国語 文法編(ジェイ・リサーチ出版 王 舟 著)
先ずご紹介するのは、ジェイ・リサーチ出版社より出版、中国人の中国語教師である王舟氏による著作”新ゼロからスタート中国語 文法編”です。
Amazonでベストセラー1位に選ばれた他、Amazonの評価も4.2/5(2024年時点)と高く、多くの支持を得ている書籍となっています。
北京生まれの中国人である王丹氏によって書かれた本書は、中国語初学者が苦戦しやすい中国語の発音と文法の両方を丁寧に解説しており、中国語ビギナーにとってとてもおすすめの書籍です。
CD付 ゼロからしっかり学べる!中国語「文法」トレーニング(高橋書店 宮岸雄介著)
続いてご紹介するのは、高橋書店より出版、宮岸雄介氏による著作”CD付 ゼロからしっかり学べる!中国語「文法」トレーニング”です。
多くの言語の入門書シリーズで知られる高橋出版の”ゼロからしっかり学べる!”シリーズの中国語版です。
コンパクトなサイズで持ち歩きがしやすく、かつ内容も分かりやすく見やすいレイアウトで書かれている為、非常にとっつきやすい参考書です。
その一方で、基礎的な中国語文法の他にも例文や単語の説明など、きちんと語学の入門書としての機能も備えています。
中国語を初めて学ぶ方や、基礎をもう一度復習したい方におすすめの書籍となっています。
すぐに話せて必ず通じる 李姉妹と基礎から中国語 音声ダウンロード付(KADOKAWA 李姉妹著)
続いてご紹介するのは、KADOKAWAより出版、李姉妹による著作である”すぐに話せて必ず通じる 李姉妹と基礎から中国語 音声ダウンロード付”です。
中国語学習チャンネルである”李姉妹ch”を運営するYouTuberとして活躍されている、中国人の姉妹であるゆんちゃん氏としーちゃん氏による中国語の参考書です。
”李姉妹ch”はチャンネル登録者数37.2万人を誇る人気チャンネルであり、彼女たちの中国語教育動画は大変わかりやすいと多くの視聴者の支持を受けています。
分かりやすいレイアウトに加えボリュームもしっかりあり、中国語の初学者から中級者まで幅広いレベルの学習者におすすめの書籍となっています。
CD BOOK たったの72パターンでこんなに話せる中国語会話(明日香出版 趙怡華著)
続いてご紹介するのは、明日香出版より出版、趙怡華氏による著作である”CD BOOK たったの72パターンでこんなに話せる中国語会話”です。
明日香出版より発売されている”たったの72パターンでこんなに話せる”シリーズの中国語版です。
このシリーズはタイトルの謳い文句の通り、少ない決まったパターンで外国語の日常会話が出来るようになるという実践的な参考書で、本書の他にも英語や韓国語、ロシア語やタイ語など、数多くの外国語が学べるシリーズとなっています。
本書は中国語初学者の他にも、ある程度中国語の文法を学んだ人が実践的な中国語を学ぶ際にも使用できる参考書です。
中国に旅行する際などに携帯しておくと、大変心強い一冊であると言えるでしょう。
まとめ
いかがだったでしょうか。
皆様もこの記事を通じて、中国語に興味を持っていただけたなら幸いです。
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
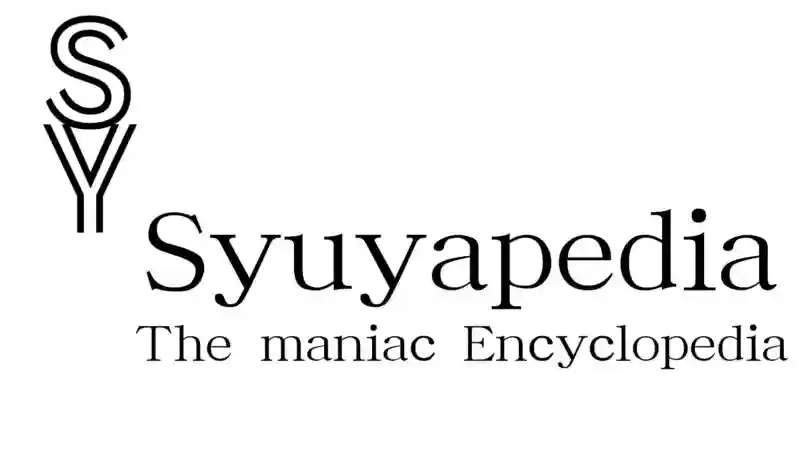

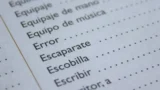

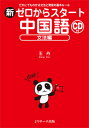





コメント